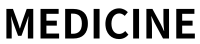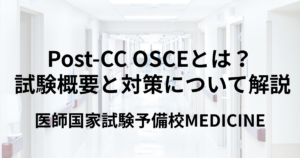OSCEの医療面接とは?概要と例題、対策方法について解説 | 医師国家試験予備校MEDICINE
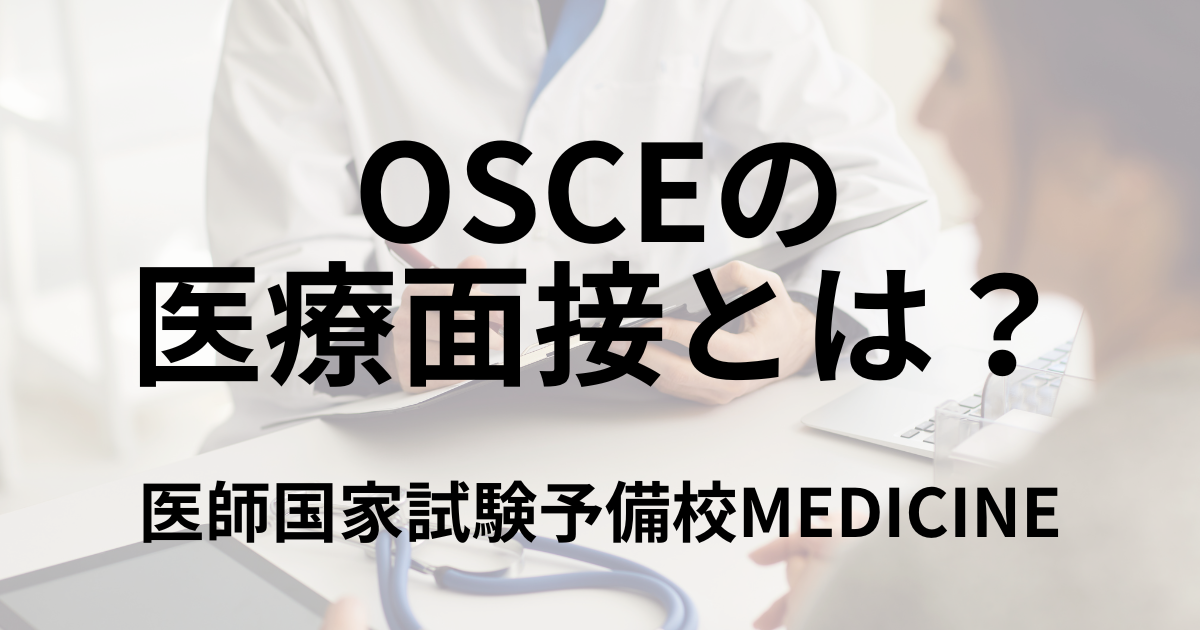
更新日:2025年11月15日
医学生にとって避けて通れない関門であるOSCE(客観的臨床能力試験)では、手技や診察技術だけでなく「医療面接」も重要な評価対象です。医療面接では、患者との適切なコミュニケーションを通じて、その後の診察や治療に必要となる情報を正確に得る能力が求められます。
本記事では、OSCEの医療面接の概要や進め方、例題、効果的な対策方法を詳しく解説します。

監修
医師国家試験予備校MEDICINE 塾長・医師 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。大手医師国家試験予備校で、在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。その後、医師国家試験予備校MEDICINEを設立し現在に至る。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
OSCE医療面接とは

「医療面接」は多くの大学で4年次に行われるOSCEの試験項目の一つです。
他の「腹部診察」、「救急」といった項目では診察や手技の手順、正確性を評価されるのに対し、「医療面接」では患者とのコミュニケーションを通じて必要な情報を収集する能力が評価されます。コミュニケーションといっても実際に患者さんに対して質問すべき内容は大部分が決められていますので、そのフォーマットに沿って面接を進めていくことが基本になります。
本番の試験は、初診外来に来た患者(模擬患者)に対して、医師の診察前に医学生が医療面接を行うという設定で行われます。求められているのは情報収集をすることであり、病気の診断をつけたり治療を考えたりするところまでは要求されません。
医療面接を行う机と椅子が用意された部屋の一角(診察前の待合室という設定)に模擬患者が待機しており、呼び出しにいくところから試験が始まります。
この記事では、以下医療面接の流れ、医学生が聞くべき内容をまとめていきます。
OSCE医療面接概要

上述の通り医学生が医療面接で聞くべき内容は基本的にフォーマット化されています。
ここでは実際の順番に則して
・オープニング、導入
・主訴、現病歴の確認
・その他病歴、関連情報の確認
・クロージング、まとめ
という順番でその内容を説明します。
オープニング、導入
患者を診察室(という設定の机、椅子)に呼び入れたらまずは名前を名乗り、自己紹介をしましょう。
続いて、本人確認のために患者さんにフルネームを名乗ってもらいます。
そして自身が医学生として医師の診察の前に医療面接を行うことを告げ、了承をとりましょう。
了承を得ることができたら、実際に患者さんについての情報収集に移ります。
初めは「本日はどうされましたか?」のようなオープンクエスチョン(自由度が大きい質問)から入ります。オープンクエスチョンに対する患者の訴えを十分に聞いたのちに「その症状についてもう少し詳しく教えていただけますか?」のようにやや自由度を絞った質問を行い、それでも足りない情報を追加で聞いていくという流れになります。
主訴、現病歴の確認

上述の導入で患者の訴えを聞いて足りなかった情報をこちらから質問して収集していきます。
現病歴について確認する項目として一般に「OPQRST」というものがあります。
・Onset(発症様式)いつごろどのように(急に、徐々になど)今回の症状が始まったのか聞く
・Provocative/palliative Factor(増悪/寛解因子) 「寝ると症状が軽くなる」、「運動すると症状がひどくなる」などのように症状を増悪させたり亜寛解させたりする因子がないか聞く
・Quality(質的内容) 痛みがどのような痛みなのか(刺すような痛み、痺れるような痛みなど)
・Region/Related Symptom(場所・随伴症状) 症状が体のどの部位に起きているのか、他に症状はないか聞く
・Severity(強さ) 痛み、症状の強さを聞く。「1〜10の10段階だとどの程度の痛みですか?」のように質問すると答えやすい
・Timing(時間経過) 症状の時間的経過を確認する。(発症からずっと続いている、昨日は少し良くなったが今日また酷くなったなど)
以上のように「OPQRST」に沿って現病歴を確認すると必要な情報を漏れなく収集することができます。この順番にこだわる必要はないので、患者さんとのコミュニケーションの流れの中で自然な順番で確認するようにしましょう。
医療面接の際はメモをする紙を一枚渡されるので、筆者は面接を始める前に紙に「OPQRST」だけ箇条書きで書いておいて、話を聞きながら埋めていくようにしていました。
その他病歴・関連情報の確認
現病歴に続いて、診察上重要と思われる情報をさらに追加で確認していきます。ここでも聞くべき内容はたくさんありますが、どれも非常に重要ですので聞き逃しがないようにしましょう。以下、必要な項目と簡単な説明を挙げておきます。
・家族歴 家族に大きな病気をしたことがある人はいるか。(父母、祖父母が亡くなっている場合死因が判明しているかも確認する)
・既往歴 患者自身が過去に大きな病気にかかったことがあるかを聞く、合わせて今まで健診などを定期的に受診してきたか、その際に何か異常を指摘されたことはあるかなどを確認する
・社会歴 飲酒/喫煙歴や仕事歴を確認する。仕事歴については「言える範囲で構いませんのでどのようなお仕事をされているか教えていただけますか?」のように聞くと良い
・服薬歴 現在飲んでいる薬を確認する
・受療行動 今回の症状に関して何か治療を受けたり、薬を服用したりしたか
・解釈モデル 今回の症状に関してどのように考えていて、どのような点が最も心配か/治療について何か要望はあるか(手術は避けたい、頻回の通院は難しいので入院にしたいなど)
・その他鑑別診断に関する情報 排便の状況、食欲・体重の変化・周りの環境の変化など 「職場の人事が最近変わって、かなりストレスを感じていた」のような情報が出てくることもあるので、環境の変化を尋ねるのは意外と重要です。
クロージング、まとめ
ここまで患者さんに質問した内容をもとに最終的な総括を行います。
「ここまでのお話をまとめさせていただきます」と断って、重要と思われる内容を簡潔に要約して話し、「今お話しした内容でお間違いないですか?」「何か付け足しておきたい内容や確認しておきたいことはありますか?」と確認します。ここで、スムーズにまとめができるように、面接中は患者さんから聞いた情報を適宜紙にメモしておきましょう。
確認ができたら「では担当医に今お伺いした内容をお伝えしますので、もうしばらくお待ちいただけますか」のように医療面接を終了します。
共感的態度について
医療面接では、必要な情報を収集する能力の他に、患者に対する態度も評価の対象になります。しっかり目を見て話す、適切な敬語を用いるなどももちろん重要ですが、「共感的態度」と呼ばれるものは他の試験項目にはない特有のものであり特に大事になります。
「共感的態度」とはその名の通り、患者の気持ちに共感する・寄り添うような態度のことです。このことをわかっているだけではなく、実際に共感的態度をとっていることをある程度試験官にアピールする必要があります。
例えば、
患者「一昨日から頭痛があります」
医学生「一昨日から頭痛があるのですね」
のように患者の訴えを復唱したり
患者「昨日は痛みが特に酷くて全く眠れませんでした」
医学生「それはお辛かったですね」
のように積極的に共感を伝えたりするようにしましょう。
医療面接の対策

医療面接では本番どのような設定の模擬患者が出てくるかわからないので、かなり臨機応変な対応が求められます。
焦らなくて済むよう以下のような準備を予めしておくと良いでしょう。
主訴に応じた質問の仕方を考える
例えば「主訴・現病歴の確認」のところで「OPQRST」という項目を紹介しましたが、具体的な質問の仕方は主訴によって大きく異なります。
「痛み」が主訴であればSのSeverityについて「痛みの程度を1~10の10段階で教えてください」と質問することができますが、「発熱」のような主訴の場合、「熱はどの程度ありますか?」「体のだるさはどの程度ですか?」などのように聞き方を変える必要があります。
また、医療面接では病気の診断をつけることは求められませんが、「鑑別診断に関する情報」を収集するためにある程度鑑別診断をあげる能力は必要です。どのような主訴の患者が来たら、どんな疾患が鑑別診断として挙げられ、どのような質問が鑑別に有用かしっかりと覚えておきましょう。
本番はかなり緊張する上、時間も限られていますので予め言い回しを含めて考えておいた方が焦らずに済むでしょう。
ロールプレイで何度も練習する
聞くべき内容、言い回しなどを覚えたらあとはひたすら実践形式でアウトプットの練習をしましょう。
友人同士で模擬患者役と医学生役に分かれて練習すると効果的です。医学生役はもちろん自身のアウトプットの練習になります。模擬患者役もシナリオ(疾患)を考え、そこから想定される質問に対する答えなどを考えることで自身の対応の幅を広げることができるでしょう。
また、医療面接を行なっている際の態度(目をしっかり合わせて話しているか、共感を感じ取れるような話し方になっているか、貧乏ゆすりや髪をいじるなどの行為が無意識に出ていないか)を客観的に評価してもらうこともとても大切です。
まとめ
この記事では医学部OSCEの試験項目の一つである「医療面接」に焦点を当てて解説しました。
何よりも大事なのは、まずどのような情報を収集することが求められているのかしっかり覚えること、共感的態度を身につけることです。
これらのことができていれば、多少ぎこちなくなったり言葉に少し詰まったりした程度では不合格になることはないと思われます。
途中で聞き逃したことを思い出した場合でも、落ち着いて話が前後する旨を伝え、聞き直せば全く問題ありません。
もちろん全てが勉強した通りにスムーズに進められることが理想ですが、本番では緊張から何かとイレギュラーなことが起こりがちです。
自分の今までの努力を信じて、冷静な対応ができるようになるくらいには繰り返し練習を積みましょう。
✖️
参考:マナーの重要性 | 理系就活のまとめとま