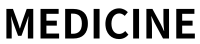ブルンベルグ(Blumberg)徴候について詳しく解説| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日:2025年11月15日
この記事では、消化管範囲で頻出の用語であるブルンベルグ徴候(Blumberg徴候)について、その背景知識となる解剖からこの兆候がみられる病気まで詳しく解説していきます。

監修
医師国家試験予備校MEDICINE 塾長 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
腹膜の解剖について
ブルンベルグ徴候についてみていく前に、まずは腹膜の解剖についてしっかり理解しておきましょう。
腹膜と腹腔臓器(小腸、横行結腸など)の関係および、解剖学的部位の名称については次のように理解しておきましょう。
①まず、腹膜自体は一つの大きな袋状の膜であると考えましょう。この袋の中の空間を「腹腔」と呼びます。

②腹腔臓器は、この袋状の腹膜に埋め込まれるように存在しています。

③袋状の腹膜に埋め込んだ際、余った2枚の腹膜は癒着しており(くっついている)この部分は間膜と呼ばれます。
間膜には、上・下腸間膜動静脈のような腹腔臓器に分布する血管が通っています。

④この状態の腹膜で、腹腔臓器に接している部分は「臓側腹膜」、それ以外の部分を「壁側腹膜」と呼びます。

体幹部の断面でみると、壁側腹膜は体壁(お腹の皮膚や背骨など)に張り付くような形で存在しています。
腹腔の背部には後腹膜空と呼ばれる空間があり、大動脈や腎臓、膵臓などの後腹膜臓器と呼ばれる臓器が存在します。


内臓痛と体性痛の違い
続いて上記の解剖学的な知識をもとに腹痛の種類を解説します。
腹痛は内臓痛と体性痛に大別されます。それぞれ以下のような特徴があります。
- 内臓痛
日常会話で使う「腹痛」はこちらの内臓痛を指すと思われます。
内臓痛は、臓側腹膜に進展、収縮、内圧上昇などの刺激が加わった際に感じられる鈍痛です。
痛みの場所がピンポイントではっきりしているわけではなく、漠然と「お腹が痛い」と感じるのが特徴です。
- 体性痛
対して、腸間膜や壁側腹膜に炎症・刺激が及んだ際に感じられる、鋭い痛みが体性痛です。
こちらは痛みの場所がはっきりしており、「お腹のこの部分が痛い」とピンポイントで指さすことができます。
この記事で扱うブルンベルグ徴候は体性痛がある際にみられる徴候です。
ブルンベルグ徴候とは
上述の通り、ブルンベルグ徴候は腸間膜や壁側腹膜に炎症・刺激が及んだ際にみられる徴候(腹膜刺激症状)の一つです。
腸間膜、壁側腹膜に炎症が及んでいると思われる部位を指でゆっくり圧迫し急激に解除した際、鋭い痛みを感じるという徴候です。
この徴候があるか確認する際には、通常4本の指を患者の腹部に垂直に立ててゆっくりと押し込んでいき、急激にその圧迫を解除し
「お腹を押した時と、離したときどちらの方が強い痛みを感じましたか?」と確認します。
「離した時の方が痛かった」という回答が得られた場合、ブルンベルグ徴候ありと判断します。
この特徴から、ブルンベルグ徴候は別名「反跳痛」とも呼ばれます。
腹膜刺激症状には他に、腹膜に炎症がある部分を圧迫した際、反射的に筋が緊張して硬くなる「筋性防御」や、常に筋が緊張し続けていて腹部が硬くなっている「板状硬」などがあります。
ブルンベルグ徴候がみられる疾患
ブルンベルグ徴候は腹膜に炎症が及んだ際見られるのは先述のとおりです。
腹膜に炎症をきたす原因は様々ありますが、重要なものの一つとして感染があります。
例えば、消化管穿孔(腸などに穴が空いて中身が腹腔内に漏れ出た状態)になると腹膜に腸内細菌による感染を引き起こしますし、手術後など腹腔内にドレーンのような人工物を長時間留置することも感染を引き起こす原因となります。
また、腹部大動脈瘤破裂、外傷、子宮外妊娠などによって腹腔内に血液が漏れ出ても腹膜を刺激し炎症を起こします。
虫垂炎、膵炎、憩室炎、腸閉塞、腸間膜虚血のような炎症を引き起こす疾患も腹膜に炎症を波及させる原因となり、ブルンベルグ徴候が見られることがあります。
まとめ
この記事では、消化管関連の疾患でよく出てくるブルンベルグ徴候についてまとめました。
徴候の説明のみでなく、周辺知識についても解説しましたので、日々の勉強にお役立ていただければ幸いです。