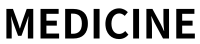理想の医師像についての小論文の考え方を解説| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日:2025年11月15日
「理想の医師像」は医学部の面接やマッチングの小論文において頻出の話題ですが、抽象的なお題であるがゆえに何をどのように書けばいいのかよくわからないという方も多いと思います。
また、「理想の医師像」は小論文だけでなく、面接においてもよく聞かれる話題です。一旦自分の中で考えをまとめておくだけでも汎用性が高く、色々な場面で使いまわすことが可能です。
この記事では、「理想の医師像」を問う小論文について
・理想の医師像の考え方
・小論文の書き方
・小論文の例文(800文字程度)
の3つの内容で解説していきます。

監修
医師国家試験予備校MEDICINE 塾長 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
理想の医師像の考え方

まずは小論文を書くにあたっての軸となる、「理想の医師像」をどのように作り上げればいいのか解説していきます。
これはどんな小論文や面接でも言えることですが、全体を通して論理を一貫させることがとても重要です。
以下で解説する3STEPの順に考えれば説得力のある論理的に一貫した「理想の医師像」を考えることができるはずです。
医師志望理由をはっきりさせる
「理想の医師像」を考えるということは、医師としてどのような人生を歩みたいのかというゴールを考えることに他なりません。
しかし、そのゴールを明確にするにはまず、「なぜ医師を志したのか」という出発点をはっきりさせる必要があります。
医師を志したきっかけの中には、必ず医師という職業に何かしらの「魅力」を感じた経験があるはずです。
その「魅力」から自分がどのような医師になりたいのか発展的に考えていくことで、スタートからゴールまで論理的に一貫した「理想の医師像」を作り上げることができます。
まずは、自分が感じたままに率直な言葉で医師の魅力を言語化し、それを小論文仕様に適切な言い換えをすれば大丈夫です。
ポイントは
・社会的な要求に一致する言い回しにすること
・ある程度一般化すること
です
具体例を示します
例1) 外科の手術が楽しそうだと思った
→ 自分の手で直接患者さんの命・生活を救える点に、医師という職業の責任とやりがいを感じた
例2) 自分が病気になった時、優しくしてくれた
→ 病気で苦しむ患者さんに身体的な治療だけでなく、精神面でも寄り添うことのできる医師に憧れを抱いた
ロールモデルを見つける
医師という職業の魅力を言語化できたところで、続いて「理想の医師像」へ発展させていきます。
ここでは医師としてのロールモデルを見つけ、理想の医師像へ発展させる方法を紹介します。
ロールモデルは必須ではありませんが、実際に医師として働いている人の考え方に触れることで、それまでなかった新しい視点に立つこともできるのでおすすめです。
先述の通り、重要なのは論理的に一貫した内容にすることです。自分が感じた「医師という職業の魅力」と関連させて「医師として目指す姿勢」について触れられると良いでしょう。
小さい頃に病気になり治療してもらったことで医師を目指すようになった、という人であればそのお世話になった医師をロールモデルに据えてみるのも良いでしょう。他にも実際に医療現場で働く医師の人生観、仕事に対する考え方などを記したエッセイは、本としてもオンラインの記事としてもたくさん出ていますので、共感できるものを一つ見つけてみてもいいかもしれません。
魅力から理想の医師像へ発展させる具体例を以下に示します。
例1)自分の手で直接患者さんの命・生活を救える点に、医師という職業の責任とやりがいを感じた
→ 僻地でその地域唯一の外科医として活躍する先生の本を読み、「地域の医療を守る」という強い責任感を医師としてのスキル向上・成長に繋げようとする姿勢に心を打たれた。自分もどのような環境にあっても常に患者さんを第一に考え、常に学び続ける姿勢を持った医師でありたいと考えた。
例2)病気で苦しむ患者さんに身体的な治療だけでなく、精神面でも寄り添うことのできる医師に憧れを抱いた
→ 小さい頃病弱だった私の治療をしてくれた小児科の先生は病院を怖がる私にも、また私の病状を不安がる母にも、丁寧な説明を心がけ恐怖・不安を払拭してくれた。患者本人はもちろんのこと、その家族の心にも寄り添い、医学的・心理的側面の双方から安心感を感じられる医療を提供できる医師になりたいと思った。
医師としての目標を加える
最後に医師としての目標、成し遂げたいことなどを加えましょう。
ここまでの2STEPでは主に、「医師として目指す姿勢」を言語化してきましたが、その内容を踏まえて最後に「医師としてどんなことをしたいか」という点に触れると説得力が増します。
この目標は具体的に医師として実行したい行為そのものでも、医師としての理念的な目標でも構いません。
これについても以下具体例を示します。
例1)どのような環境にあっても常に患者さんを第一に考え、常に学び続ける姿勢を持った医師でありたい
→どのような環境にあっても常に患者さんを第一に考え、常に学び続ける姿勢を持った医師でありたいと考えた。1人の外科医として技術を磨くのはもちろんのこと、自身の学び続ける姿勢を以て後進の育成にも貢献できる医師が理想であると考える。
例2)患者本人はもちろんのこと、その家族の心にも寄り添い、医学的・心理的側面の双方から安心感を感じられる医療を提供できる医師でありたい
→患者本人はもちろんのこと、その家族の心にも寄り添い、医学的・心理的側面の双方から安心感を感じられる医療を提供できる医師になりたいと考えた。患者さん本人とその家族の心の支えとなり、皆が前を向いて生きていくことのサポートができる医師が私の理想の医師像である。
小論文を書く際のポイント

前章では、小論文の軸となる「理想の医師像」をどのようにして考えるかという点について解説してきました。
ここからは、その軸を元にどのように小論文を展開していけば良いのか3つポイントをお伝えします。
主題を必ず一つ決める
小論文を書く際のポイント1つ目は、「主題を一つ決める」ことです。
繰り返しになりますが、小論文を書く際は最初から最後まで論理が一貫していることが非常に重要です。
「主題」というのは、「小論文を通して最も伝えたい1番の主張」ということになります。
小論文に書く内容は、最終的に全て主題に帰結することを意識して書き進めると、論理的な一貫性を保つことができます。
難しく考える必要はなく、前章で考えた「理想の医師像」の中で、自分が最も重要と考える部分を主題に据えれば問題ないはずです。
例1)常に学び、成長し続ける医師
例2)患者・家族の心の支えとなる医師
などで良いでしょう。
自身の経験や強みと関連づける
小論文を書く際のポイント2つ目は、自身の経験や強みと関連づけることです。
ここまでは「理想の医師像」の本論に近いところを解説してきましたが、ここからは、その本論をサポートし小論文としての説得力を上げる方法について解説していきます。
自分の考えた「理想の医師像」をただ述べるだけでは、机上の空論・理想論に過ぎないと捉えられてしまう可能性があります。
字数制限との相談にはなりますが、「理想の医師像」が醸成された過程を自身の経験を踏まえて書く、「理想の医師像」を達成する上で役に立つ自身の強みを書く、などの工夫を入れられると良いでしょう。
ただ、前述の主題と全く関係のない経験・強みを書くのはNGです。あくまでも、主題をサポートし説得力を上げるためのものです。
これも具体例を2つ示します。
例1)常に学び、成長し続ける医師でありたい
→ 部活の主将として勉強と両立させつつ毎日欠かさず向上心を持って自主練に励んだ。主将自ら上達への意欲を行動で示したことで、チーム全体のモチベーション上昇にも繋がった
例2)患者・家族の心の支えとなる医師でありたい
→ 家庭教師で生徒に指導するだけでなく、授業後には保護者にその日のフィードバック、今後の方針伝達を逐一行い、家族全体が見通しを持って受験に臨めるようにサポートした
社会的な背景を加える
小論文を書く際のポイント3つ目は社会的な背景を加えることです。
医師という職業の本分は社会的な要求に応えることです。
自分の考える「理想の医師」がなぜ必要とされているのか、簡単にでも良いので社会的な背景に触れつつ書くことができれば説得力はさらに上がります。
例1)後進の育成にも貢献できる外科医を目指したい
→現在日本では深刻な外科医不足が問題になっていることについて触れる
例2)患者・家族の心の支えとなる医師でありたい
→高齢化社会で長期療養・在宅医療が増加し、家族への精神的なケアが今まで以上に重要になっていることについて触れる
小論文の例文

最後に、ここまで挙げた例1、例2をもとにそれぞれ800字程度の小論文の文面例を示します。
例1
私が考える理想の医師像は、どのような環境においても常に患者を第一に考え、学び続ける姿勢を持った医師である。医療技術は日々進歩しており、学ぶ努力を継続することは、患者の命を預かる医師としての使命であると考える。
私が医師を志したのは、高校時代に外科手術の映像を見たことがきっかけだった。自らの手で直接患者の命を救う姿に、医師という職業の責任とやりがいを感じた。以後、外科医として社会に貢献したいという思いを抱くようになった。そうした中で、僻地医療に携わる外科医の著書を読んだ。限られた医療資源の中でも「地域の医療を守る」という使命感を胸に、自己研鑽を続ける姿に強く感銘を受けた。私もこのように、環境に左右されず常に学び続ける姿勢を貫きたいと思うようになった。
このような姿勢は私のこれまでの経験にも通じている。部活動の主将を務めた際には勉強と両立させつつ、毎日欠かさず自主練に励んだ。主将自ら向上心を行動で示すことで、チーム全体の士気も高まった。この経験を通じて、自分の成長が周囲に良い影響を与えることを実感した。
現在、日本では外科医の不足が深刻化している。私は、一人の外科医として技術を磨くだけでなく、後進の育成に尽力し、少しでも日本の外科医不足解消に貢献したいと考えている。常に成長し続け、自らの成長を社会に還元できる医師こそ、私の理想の医師像である。
例2
私が考える理想の医師像は、患者本人だけでなく、その家族の心にも寄り添い、医学的・心理的の両面から安心感を与えられる医師である。医療は単に病気を治すだけでなく、患者と家族の不安を和らげ、心の支えとなることも重要な役割であると考える。
私がこのような考えを抱くようになったのは、自身の幼少期の経験がきっかけである。私は小さい頃、病弱で入退院を繰り返していた。その際、主治医の先生は私に対してはもちろん、私の病状を不安に思う母にも丁寧に説明をしてくれた。その姿勢のおかげで、病院への恐怖が和らいだだけでなく、家族全体が安心して治療に臨むことができた。私はこの体験を通じて、医学的知識だけでなく、患者と家族の心にも寄り添える医師に憧れを抱いた。
この姿勢は、私が家庭教師として働いた際の経験にもつながっている。私は生徒への指導だけでなく、授業後には保護者にその日の進捗や今後の方針を丁寧に伝えるようにしていた。その結果、生徒本人だけでなく家族も安心して受験に臨むことができた。相手の不安に耳を傾け、信頼関係を築くことの大切さを学んだ。
現在、日本は高齢化の進行により、在宅医療や長期療養が増加している。病気と長く向き合う患者と家族にとって、医師の言葉や態度が心の支えとなる場面が増えている。こうした時代だからこそ、身体だけでなく心にも寄り添う医師が求められていると感じる。私は、患者と家族の双方が前を向いて生きていけるよう支えられる医師が理想であると考える。
まとめ
この記事では「理想の医師像」というテーマの小論文について、考え方から小論文の書き方まで解説してきました。
「理想の医師像」というテーマは「医師としての目標」「医師を志した理由」など他のテーマにも通ずる部分が大きく、一度深く考えてみる価値はあるはずです。
是非医学部受験、マッチングの際などの参考にしてください。
✖️