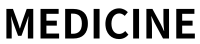虫垂炎の圧痛点と徴候の覚え方を解説| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日:2025年11月15日
虫垂炎はCBTや医師国家試験において比較的出題頻度の高い消化器疾患です。
虫垂炎には特徴的な痛みや徴候がいくつかあります。それらを覚えておくだけで、実際の問題に登場する虫垂炎は簡単に見分けることができ、得点源とすることができます。
この記事では、まず背景となる解剖学的な知識を確認したうえで、圧痛点や徴候についてそれらの知識をベースに解説していきます。

監修
医師国家試験予備校MEDICINE 塾長 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
虫垂炎とは

まずは虫垂炎という病気について基本的な知識を解説していきます。
ここでは、下部消化管の解剖、病態の2点をみていきましょう。
下部消化管の解剖
「下部消化管」は消化管全体のうち、胃より先の部分を指し、大きく小腸と大腸に分かれます。
この小腸と大腸は部位によってさらに以下のように分けられています。


- 小腸
小腸は全体でおよそ6mの長さがありますが、以下のように3つの解剖学的名称で区分されています。
十二指腸 ・・・胃の出口(幽門)の直後から始まってTreitz靭帯まで続いており、長さはおよそ25cmです。
膵液や胆汁が分泌される「Vatar乳頭」が存在します。
空腸 ・・・Treitz靭帯以降の小腸の口側およそ2/5を空腸と呼びます。腸液による消化と吸収が主な役割です。
回腸 ・・・小腸の肛門側3/5が回腸と呼ばれます。空腸と回腸の明確な境目はありません。大腸との接合部に存在する「回盲弁」までが回腸です。
- 大腸
大腸は大きく盲腸、結腸と直腸に分けることができ、結腸はさらに細かく4つの部位に分かれます。
上行結腸 ・・・大腸の始まりの部分で、体の右側を下腹部から中腹部付近まで登っていくように存在します。
盲腸 ・・・回腸が開口している部分(回盲弁)から上に登っていくのが上行結腸ですが、盲腸はそこから下に向かって存在する5~6cmの部分です。
この記事で扱う虫垂は盲腸の一部分からさらに伸びるように存在している長さ5〜10cm、管腔状の構造物で右下腹部に存在します。
横行結腸 ・・・上行結腸に続く部分で、中腹部を体の右側から左側へ横に走っています。
下行結腸 ・・・横行結腸に続く部分で、体の左側を中腹部付近から下腹部まで下降していくように存在します。
S状結腸 ・・・下行結腸が左下腹部で終わるところから、体の中心部まで肛門に向かう形で存在します。
直腸 ・・・肛門の直前の部分です。
虫垂炎の病態
続いて虫垂炎の病態をみていきましょう。
虫垂炎とは名前の通り、虫垂に炎症が発生している状態です。
炎症が起こる原因ははっきりとはわかっていませんが、糞石などにより虫垂の管腔が詰まってしまい、内部で細菌が繁殖することにより起こると考えられています。
初期は虫垂だけの炎症で止まりますが、進行すると虫垂の壁が破れて細菌や膿などの内容物が腹腔内に漏れ出てしまうことがあり、腹膜炎などの重篤な合併症を引き起こす原因にもなります。
虫垂炎の症状・徴候

続いて虫垂炎で見られる症状・徴候を解説していきます。
基本的な症状としては、心窩部や腹部の痛み、発熱、悪心・嘔吐、食欲不振などがあります。
以下これ以外の特徴的な症状を説明します。圧痛点(McBurney点、Lanz点)、各種徴候の名前もここで出てきますので覚えておきましょう。
腹膜刺激症状
初期の虫垂炎は臓側腹膜の炎症で始まりますが、炎症が壁側腹膜に波及すると「腹膜刺激症状」が見られるようになります。
腹膜刺激症状には
・Blumberg徴候 腹部を押した時よりも離した時が痛い
・筋性防御 腹部を押そうとすると筋肉が緊張して硬くなる
・板状硬 筋性防御がさらに進み、腹部が一枚の板のように硬くなる
などがあります。
これらについては、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらを参考にしてみてください。
ブルンベルグ(Blumberg)徴候について詳しく解説| 医師国家試験予備校MEDICINE
圧痛点について
虫垂炎では腹部の触診で押した際に特に強い痛みを感じる「圧痛点」と呼ばれる点が2つあります。
まずはそれらの点の場所を説明します。

- McBurney点
「マクバーニー点」と読みます。
右上前腸骨棘(腰骨の出っ張っている部分)と臍を結ぶ線の外側1/3の点で、虫垂の根本部分に相当する場所です。
- Lanz点
「ランツ点」と読みます。
左右の上前腸骨棘を結ぶ線の右側1/3の点で、虫垂の先端部分に相当する場所です。
虫垂炎で見られる徴候
続いて虫垂炎で見られる徴候を解説していきます。
「徴候」とは痛みのように患者本人が自覚できる「症状」とは区別され、診察によって客観的に確認できる身体所見を指します。
虫垂炎に比較的特異的な(他の疾患では見られにくい)徴候として以下の4つが挙げられます。
- Rosenstein徴候

左側臥位(左肩を下にして横向きに寝た状態)になると痛みが増強する徴候です。
これは、重力によって虫垂が引き延ばされることによって発生しています。
- Rovsing徴候

左下腹部を下から上に向けて圧迫すると右下腹部の痛みが増強する徴候です。
左下腹部は下行結腸の終端部にあたり、そこを下から上に向かって圧迫すると結腸内のガスが回盲部(虫垂がある部分)に向かって移動するため痛みが増強します。
- Psoas徴候(腸腰筋徴候)

患者を左側臥位に寝かせた状態で、右の股関節を過伸展(脚を大きく後ろに引く動き)させた時に、痛みが増強する徴候です。
右の腸腰筋(上半身と下半身を結ぶ大きな筋肉)が伸展によって虫垂に触れる位置関係にある場合や、虫垂の炎症が腸腰筋にまで及んでいる場合には有効です。
- Obturator徴候(閉鎖筋徴候)

患者を仰臥位(仰向けの状態)にして、右脚の股関節と膝を曲げ、股関節を内旋(膝を内側に捻る動き)させると、痛みが誘発される徴候です。
これも閉鎖筋に炎症が及んでいる場合に陽性になる徴候です。
まとめ
この記事では、虫垂炎について解剖的な背景知識から、圧痛点、兆候まで解説してきました。
実際の症例問題では「右下腹部痛」というキーワードでしっかり虫垂炎を疑うことができれば、かなりわかりやすく得点源になる部分です。
徴候については名前だけでなく、「なぜそのような徴候が見られるのか」という点までしっかり理解しておくと忘れづらいと思います。
✖️