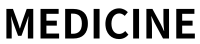解剖学の勉強におすすめのアプリとわかりやすい本を紹介| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日:2025年11月15日
解剖学は基礎医学の中で最も要求される暗記量が多い科目の一つです。
医学部では、実際の人体を眼で見ながら解剖学を学ぶ人体解剖の機会が一度だけありますが、その後の定期試験や CBT、国家試験では座学で学んでいく必要があります。
この記事では、解剖学を学ぶにあたって理解の助けになるようなアプリと本をそれぞれ3つずつ紹介します。

監修
医師国家試験予備校MEDICINE 塾長 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
解剖学の勉強法

まずは、解剖学をどのように勉強していけば良いのか、筆者が実際に勉強した手順に沿って一通り解説します。
状況にもよりますが、基礎医学の勉強をするにあたって教科書を一冊通読して全てを暗記するのはあまり効率がいい勉強の仕方とは言えません。
筆者は問題を解くにあたってのベースとなる、基本的な解剖の知識を以下で説明する通りに勉強した上で、過去問を使って重視され得るポイントを掘り下げて勉強していくというやり方をしていました。
後ほど紹介するアプリや本は勉強をしていく中で、解剖学的な構造などを視覚情報で理解するための補助的な道具として用いるのがおすすめです。
解剖実習を真面目にやる
解剖学を勉強する始めのステップは解剖実習を真面目にやることです。
解剖実習は実際の人体を使って勉強することができる唯一の機会です。
予習した上で実習に臨み、何を見ているのか理解しながら解剖して目に焼き付けることで、のちの座学での勉強を効率的に進めることができます。
さらに、自らの手を使って組織を剥離したり構造物を見つけたりする体験そのものが、知識の定着に大きく役立ちます。
例えば、皮膚切開後にどの筋肉や血管がどの順番で現れるのか、ある神経がどの筋肉の間をどのように走行しているのかなど、自分で解剖する過程で自然に得られる理解は、教科書の写真や文章を眺めるだけでは得がたい深い記憶として残り、人体の立体的な構造がより明確に把握できるようになります。
骨の名前、関節の構造を覚える
ここからは実習ではなく座学で解剖学を勉強する際のステップになります。
筋肉の名前や、その筋肉によって作られる動き(作用)、支配神経など筋肉関係の知識は、解剖学で覚えるべき事項のかなりの割合を占めています。
骨は筋肉の起始停止や作用を理解する上での必須項目であるためまずはここから覚えていきます。
大事なのは、骨の名前とあわせて関節の構造も理解することです。
特に股関節や肩関節で骨がどの部分にはまっているのか、肘関節や膝関節で骨同士がどのように接しているのかなど、細かく確認しなければ見落としてしまう点がいくつもあります。
筋肉の起始・停止、作用、神経支配の順に覚える
骨と関節について理解したら次は筋肉について勉強していきます。
まずは筋肉の起始・停止を覚えましょう。
筋肉は複数の異なる骨に跨る形で存在します。起始・停止それぞれについてどの骨のどの部分なのか(前面なのか背面なのか)、解剖学的な名称がついている部位(肩甲骨の烏口突起など)であればそこまで覚えましょう。
次に作用を覚えます。
基本的に、起始・停止を覚えていれば作用はある程度直感的に理解できるはずです。筋肉が収縮すれば起始部位と停止部位の距離が短くなるような運動が発生しますので、それが作用ということになります。
最後に支配神経を覚えましょう。
似たような作用を持つ筋肉は同一の神経に支配されているということがよくあります。作用を覚えた上で支配神経を覚えるのはそのためです。
血管を太い血管の枝分かれで覚える
筋肉を覚えたら次は血管の解剖を覚えていきます。
血管は、太い血管の枝分かれで覚えるのがおすすめです。
まずは、大動脈からどんな血管が枝分かれしているのか覚えます。
続いて
・内/外頸動脈
・鎖骨下動脈
・腹腔動脈
・内/外腸骨動脈
のように大動脈から枝分かれする太い血管がどのような枝を出しているのか覚えましょう。
静脈についても同様の方法で覚えると体系的に理解することができます。
腹部の臓器は膜との関係を理解する
最後に胸腹部の臓器についてです。
消化管のような臓器は、腹腔内でのおおよその位置関係を覚えることも大切ですが、腹膜との関係がわかればより理解が深まります。
それぞれの臓器がどのように膜に覆われているのか、もしくは膜の裏側に位置しているのか(後腹膜臓器)、血管は膜のどの部分を走行しているのか確認しながら勉強すると良いでしょう。
腹膜については以下の記事の初めに簡単に解説していますのでもしよければ参考にしてみてください。
ブルンベルグ(Blumberg)徴候について詳しく解説| 医師国家試験予備校MEDICINE
解剖学のおすすめアプリ

ここからは本題である解剖学を勉強するにあたって役にたつおすすめのアプリを3つ紹介します。
それぞれの特徴も解説しますので、ご自身の利用目的に合わせて選んでみてください。
骨、筋肉、血管、神経、臓器などから必要な組織だけを選んで表示できたり、自由に拡大・縮小、回転ができる点などはどのアプリも共通しています。
Anatomy learning

1つ目のアプリはAnatomy learningです。
こちらのアプリの特徴は、ダウンロードが無料で各機能を必要に応じて課金してアンロックしていく形式です。
今回紹介する3つのアプリの中では、日本語機能も充実しており最も初学者向けと言えるアプリです。
ただ、本格的に解剖学を勉強する際に使おうとすると機能的に少々物足りなさを感じる部分があるかもしれません。
このアプリの無料機能を使って、解剖学のアプリがどのようなものなのか試してみて、使いたいと思えば以下で紹介する2つのアプリのどちらかを購入するという方法がおすすめです。
ヒューマンアナトミーアトラス

2つ目のアプリは「ヒューマンアナトミーアトラス」です。
このアプリの最大の特徴は、買い切り型で購入時にお金を払えばずっと使い続けることができるという点です。
さらに、毎年セールを実施しており、通常3~4000円程度かかるところが時期によっては300円程度とは買うの値段で購入することができます。
機能面では、マクロな構造だけでなく肝臓の小葉構造や腎臓のネフロンなどミクロな構造の解剖も収載しているほか、3D解剖のクイズをできるという特徴もあります。
ある程度本格的なアプリで費用を抑えたいという方におすすめです。
complete anatomy

3つ目のアプリはcomplete anatomyです。
今回紹介する3つのアプリの中でこのcomplete anatomyが最も本格的、実践的な機能を備えたものになります。
大学が協定を結んでいて、在籍する学生は無料で使えるということもあるようなので是非一度確認してみてください。
最大の特徴はCTやMRIの断面画像と解剖の3Dモデルを比較してみることができる点です。
一見すると何の臓器が写っているのか分かりにくいCT画像もこのアプリを使いながら勉強することで、実際の人体の構造とリンクさせて読めるようになります。基礎医学の解剖学だけでなく、臨床医学を勉強するようになってからも使えるというのは大きなメリットでしょう。
ただ、すべての機能、解剖学的名称が英語でしか表示されないため、ある程度解剖学に熟達した人でないと使いこなすのは難しいかもしれません。
解剖学のおすすめの本

続いて、解剖学を勉強する際におすすめの本を3冊紹介します。
ここで紹介する3つの本はそれぞれ利用目的が異なりますので是非一度目を通してみてください。
解剖実習の手引き

画像:isho.jpより
おすすめの本1冊目は「解剖実習の手引き」です。
こちらは、大学での解剖実習の際に手順書として購入を求められるケースも多いと思います。
利用方法は以下の2つです。
・解剖実習を行う前に、その日どのような構造を実習で同定するのか予習する
・実習後に手順などを読み直して、実際に解剖していた時の「景色」を思い出す。
初めに述べた通りですが、解剖実習で自分の手を動かして作業することが知識の定着に繋がります。
グレイ解剖学
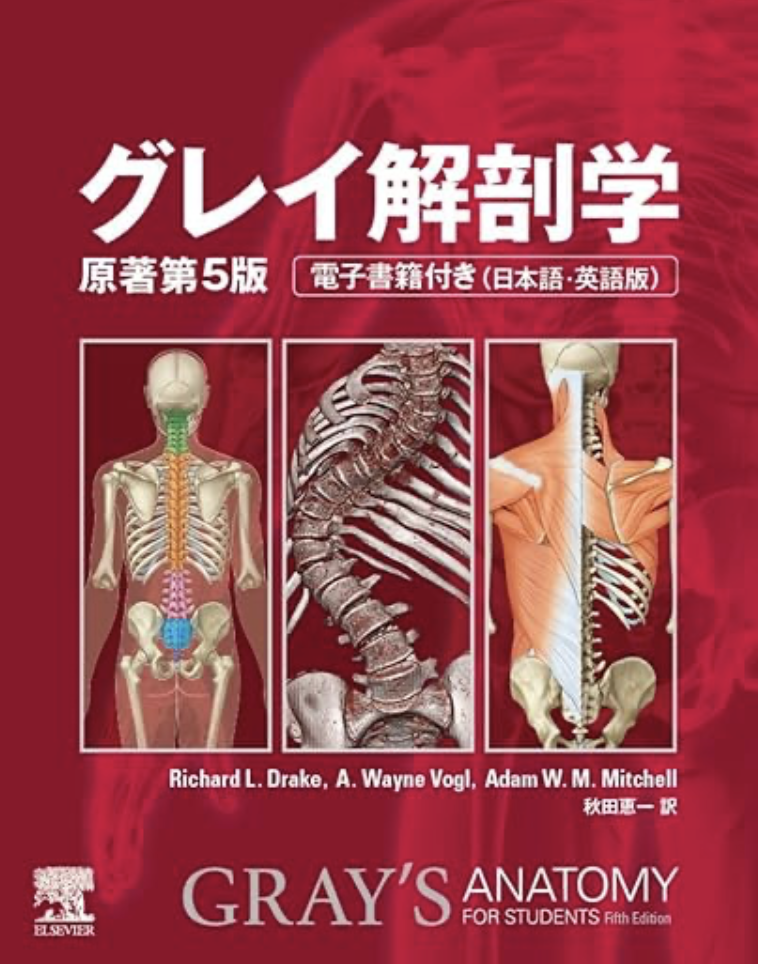
画像:Amazonより
2つ目は「グレイ解剖学」です。
グレイ解剖学は教科書という扱いで、解剖学を勉強する際の道標的な役割と、辞書的な役割の二つで使うことができます。
ただ、これは医学全般に言えることですが、教科書を丸々通読しようとすると莫大な労力がかかるうえすべてを暗記することはできず、試験対策としては効率が悪くなってしまいます。
そこで、教科書はどのような項目・分野を勉強すればいいのか確認する&わからないことがあったときに辞書的に用いるという使い方がおすすめです。
プロメテウス解剖学アトラス
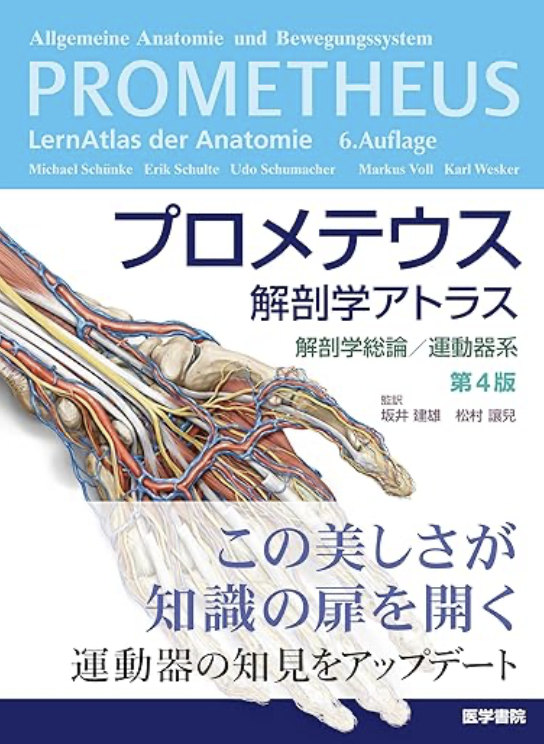
画像:Amazonより
3つ目は「プロメテウス解剖学アトラス」です。
こちらの本はアトラス(図譜)という扱いになります。
勉強する時に出てきた解剖学的構造について、実際の人体の写真や図をみて詳細に理解したいというときに用いるというのが正しい使い方です。
こちらも教科書同様通読して勉強するものではありません。
まとめ
この記事では解剖学の勉強の仕方、および勉強するにあたっておすすめのアプリと本を紹介してきました。
解剖学は勉強する範囲が非常に広く、覚える内容も多岐にわたるためとても負担が大きい科目です。ぜひこの記事の内容を参考にして自分なりの効率的な試験対策法を作ってみてください。
✖️