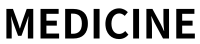脳の働きの覚え方 大脳皮質の解剖と機能局在について解説| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日:2025年11月15日
脳は人間の生命維持に必要な機能をたくさん担っていますが、その機能の詳細や、局在は複雑であまりしっかりとは覚えていないという人も多いと思います。この記事ではその脳の中でも最大の体積を占める大脳に焦点を当てて、解剖と機能について解説していきます。

医師国家試験予備校MEDICINE 塾長・医師 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。大手医師国家試験予備校で、在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。その後、医師国家試験予備校MEDICINEを設立し現在に至る。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
大脳皮質の分類
そもそも脳は1000億個以上もの数の神経細胞が集まってできた器官です。その脳のうち最大の体積を占めているのが大脳と呼ばれる部分です。
この記事では詳しくは触れませんが、大脳以外に小脳、脳幹などが脳に含まれています。
大脳の表面部分は神経細胞の中でも細胞体の部分が多く集まってできており、皮質(灰白質)と呼ばれます。皮質に存在する神経細胞は、場所によって「視覚情報の処理」「運動の指令」など役割が異なっています。これを「機能局在」と言います。
一方、大脳の深部は神経細胞の軸索(神経細胞間で情報をやり取りするための突起)の束であり、髄質(白質)と呼ばれます。
この記事では大脳の皮質に焦点を当てて解説します。
まず導入として、大脳皮質の分類を説明します。
大脳皮質は大きく「新皮質(等皮質)」と「不等皮質(原皮質+古皮質)」に分けることができます。
- 新皮質は大脳皮質の95%程度の面積を占めており、頭蓋骨を開けたときに表面から見える部分はほとんど新皮質です。新皮質は運動、感覚、高次脳機能などの機能を担っています。
- 一方、不等皮質は記憶を担う「海馬」や嗅覚を担う「嗅脳」など大脳の内側にある部位からなります。これらの部位は後ほど説明する「大脳辺縁系」と深く関わっています。
まず、ここまでは大脳の外側表面が「新皮質」、内側表面が「不等皮質」と呼ばれ、担っている機能が大きく違うということをざっくり理解しておけば大丈夫です。
新皮質の解剖
ここでは新皮質の解剖学的名称について解説します。
新皮質は4つの「脳葉」と呼ばれる区分に分かれており、脳葉の間には溝が走っています。まずはこれらの名称を覚えましょう。

上図の通り、大脳の表面には「中心溝(ローランド溝)」「頭頂後頭溝」、「シルビウス裂(外側溝)」と呼ばれる3つの肉眼的に観察可能な溝があります。
これらの溝が大脳表面を「脳葉」に分けています。
脳葉の名称は比較的単純で、前頭部にあるのが「前頭葉(ピンク色)」、頭頂部にあるのが「頭頂葉(緑色)」、後頭部にあるのが「後頭葉(黄色)」、側頭部にあるのが「側頭葉(青色)」です。
このような名称をつけて区別するのは、脳葉ごとに担っている機能が異なるからです。これについて次の「新皮質の機能地図」で解説します。
ここでは、大脳皮質が「溝」によって、「脳葉」という領域に区分されること、その脳葉ごとに異なる機能を持っていることを押さえておきましょう。
新皮質の機能地図
上述の通り新皮質は脳葉ごとにそれぞれ異なる複数の機能を担っています。一つの脳葉が一つの機能だけを担っているわけではなく、各脳葉の中でも領域によって機能は異なります。(例えば頭頂葉の中には、感覚を司る領域と、情報の統合を司る領域が存在します。)
ここでは機能ごとに脳のどの領域が司っているのか(機能地図)、その機能が障害されるとどのような症状が現れるのかなどを解説します。
運動野
運動野は、その名の通り運動に関する指令を発している場所です。

「運動野」に分類される領域は複数存在しますが、最も重要なのは「一次運動野」です。
「一次運動野」は実際に運動を行う筋肉に対し、動きの命令を発する場所です。(例えばものを掴もうとした時には、一次運動野から掌の筋肉に「収縮しなさい」という命令が出されます。)
この一次運動野は、前頭葉の中でも中心溝に最も近い位置、「中心前回」と呼ばれる縦に細長い領域に存在しています。
一次運動野の中でも、さらに細かく「手を支配する領域」「顔を支配する領域」のように体の部位ごとに支配する領域が分かれています。
一次運動野のどこの領域が体のどこの部分を支配しているのか現したのが「ホムンクルス」と呼ばれる図です。

手や唇、舌など複雑な動きが要求される部位は体の実際の表面積に対して、支配している脳の領域が広くなっています。
一次運動野は、左右の大脳両方に存在しますが、どちらも対側の筋肉を支配しています。右大脳の一次運動野は左半身の筋肉に対し指令を送り、左大脳の一次運動野は右半身の筋肉に指令を送ります。そのため、片側の一次運動野が障害されると反対側の半身麻痺が起こります。
感覚野
感覚野は種々の感覚を司る領域で、ここでは体性感覚、視覚、聴覚、味覚について説明します。

- 一次体性感覚野
一次体性感覚野は、頭頂葉の中心溝に最も近い位置「中心後回」に位置する縦に長い領域です。
一次運動野が存在する中心前回と一次体性感覚野が存在する中心後回は中心溝を挟んで隣り合っています。
一次体性感覚野は温・痛・触覚、深部感覚を司っており、一次運動野と同じように体の部位ごとに支配する領域が決まっています。
障害されると、感覚に異常が生じます。
- 一次視覚野
一次視覚野は後頭葉に存在する領域でその名の通り網膜が感じた視覚の情報を受け取っています。(上図青色の領域)
両眼の網膜の左半分が受け取った情報は右の一次視覚野へ、右半分が受け取った情報は左の一次視覚野へ送られます。
そのため、片側の後頭葉が障害されるとその反対側の半分が見えなくなる「同名半盲」という状態になります。
- 一次聴覚野
一次聴覚野は側頭葉の上部、シルビウス溝に埋もれるように存在する領域で、聴覚の情報を受け取っています。(上図緑色の領域)
聴覚はここまでに扱った運動、体性感覚とは異なり、片方の耳で感じた聴覚の情報は左右両方の聴覚野に送られます。
聴覚野が受け取った時点ではまだ情報はただの「音」でしかなく、「言葉」としての意味は持っていません。
この音を意味のある言葉として理解する過程は言語野という別の領域が行っています。
- 味覚野
味覚野はここまであげた3つの感覚野に比べると重要度は少し下がります。
体性感覚野の下あたりがシルビウス溝の中に隠れた位置にあるということを覚えておけば大丈夫です。(上図赤色の領域)
ここで扱った感覚野は一次体性感覚野、一次視覚野、一次聴覚野のように「一次」が多くついていましたが、一次からさらに情報を受け取り高度な処理を行う「二次」の領域も存在します。どれも一次に比べると重要度は低いですので概観をつかむ上では覚えなくても大丈夫です。
連合野
連合野はここまで扱ってきた情報を複数統合して処理している領域で、認識、思考といったいわゆる高次脳機能を担っています。
ここでは、頭頂連合野、前頭眼野、前頭前野の3つを扱います。

- 頭頂連合野
頭頂連合野は一次体性感覚野と視覚野の間に位置し、この二つの領域から情報(すなわち対側の体性感覚、視覚の情報)を受け取って空間認識を行う役割を持ちます。(上図青色領域)
片側の頭頂連合野が障害されると、反対側の空間と体が認識できなくなり、半側空間無視と呼ばれる特徴的な症状が発生します。
半側空間無視では
・自分の左腕、左足の存在を認めない/自分のものでないと感じる
・左半身だけ服を着ない(着衣失行)
・皿の右半分のご飯しか食べない
などの症状が発生します。
- 前頭眼野
前頭眼野は前頭葉に位置する領域で、関心のある視覚刺激を視野の中心に保つ働きをしています。(上図赤色領域)
急激に顔の向きを変えたりしても、視野が大きくぶれることがないのは前頭眼野の働きです。
- 前頭前野
前頭前野は他の領域で統合された情報をもとにとるべき行動などを判断する場所です。(上図ピンク色領域)
思考や自発性、理性、創造性など「人間らしさ」を生んでいる領域といえます。他の動物に比べて霊長類、特に人間で発達しています。
前頭前野の機能が障害されると、周囲に全く無関心になったり、几帳面だった人が急に無計画になったり、非常に幼稚で楽観的になったりと「生きてはいられるが、人としての特徴が失われた状態」になってしまいます。
言語野
言語野は言語に関する情報、指令を司る領域ですが、ここまで登場した領域とは異なり、優位半球と呼ばれる片側にしかないという特徴があります。
優位半球とは言語、計算、書字といった分析的な機能を担う側で、多くの人は左脳が優位半球となっています。
反対側を劣位半球と呼び、芸術的な表現に関わっていると言われています。
言語野にはWernicke野とBroca野の二つがあります。それぞれの機能の違いと、障害された時に起こる症状を理解することが大切です。
- Wernicke野(感覚性言語野)
wernicke野は側頭葉の上側に位置し、聴覚野から入力を受け、話された言葉の意味を理解する役割を担っています。
- Broca野(運動性言語野)
broca野は前頭葉の前頭連合野の一部で、Wernicke野から入力を受けて発話に関わる機能を担っています。
broca野のすぐ横には喉、唇、舌など一次運動野の発声に関わる領域が存在しており、密接に関係していると考えられています。

wernicke野、broca野が障害されるとともに「失語」と呼ばれる症状が起きますが、その種類が異なります。
wernicke野だけが障害されると話された言葉や書かれた文字の意味は理解できなくなります。broca野は正常であるため流暢な発話は可能ですが、wernicke野が障害されているため発話される内容は意味のない言葉、音になってしまいます。
一方、broca野だけが障害されると流暢な発話ができなくなりますが、話された言葉の意味は理解できる状態になります。これをbroca失語と呼びます。
大脳辺縁系の解剖
ここまでは大脳皮質のうち新皮質について扱ってきました。ここからは、残りの不等皮質が大きく関わっている大脳辺縁系に焦点を当てて見ていきます。
大脳辺縁系の範囲は明確な定義はないようですが、ここでは上に示す図をもとに、嗅球、視床、海馬、扁桃体、脳弓、帯状回の位置関係を確認しておきましょう。

鼻の中にある嗅上皮の嗅細胞は篩骨を通して軸索を伸ばしており、その行き先が嗅球であり、嗅覚情報の入力を受けています。
大脳の内側中央に1対の視床があり、左右から取り囲むように海馬が存在しています。扁桃体はこの海馬の先端に乗るような形で存在しています。
視床の上を通るような形で存在するのが脳弓と帯状回です。
ここまであげたものはお互いに複雑なネットワークを形成しており、次の項目で述べるような高度な機能を担っています。
大脳辺縁系の機能
大脳辺縁系の機能は記憶、情動の発現、動機付け、嗅覚情報の処理など様々ありますが、これらの機能を担う脳部位はお互いに結びつき合っています。
「情動」とは怒り、恐れ、攻撃、逃走などを指し、生物としての生存本能と強く関わっているとされています。
以下特に重要な記憶、情動、嗅覚の3つについて見ていきます。
特に記憶、情動のメカニズムはとても複雑ですので関わりが深い脳部位を覚えておくだけでも十分かと思います。
記憶
記憶の機能で最も重要なのは海馬です。
海馬はいわゆる「短期記憶」と「長期記憶」をつなげる役割を担ってなます。
自分の体験を通じて覚えた記憶などは一旦この海馬に蓄積された後、整理されて最終的に大脳に保存されていると言われています。
海馬が示す特徴的な性質の一つに長期増強と呼ばれるものがあります。
長期増強とは、2つの神経細胞が長期にわたって同時に刺激されることによって、その2つの細胞間の連絡が強化されるという性質です。この長期増強は長期記憶と多くの共通点を持つことから「記憶」と呼ばれる現象を構成する主要な機構であるとされています。
情動
情動は上述の通り、怒り、恐れなど生物の生存本能に関わる感情のことです。
情動に最も深く関わっているのは扁桃体です。
情動は海馬、帯状回を含む「パペッツの情動回路」と呼ばれる回路で、視覚、嗅覚などの感覚刺激の入力を処理することで発生します。

例えば、「危険な動物を見る」という視覚情報が入ってきたときに「逃げよう」とする行動は扁桃体で発現する情動がもとになっています。
扁桃体は次に説明する嗅覚との結びつきも強く、嗅覚情報によって誘発される性行動、飲食行動の制御などにも関わっています。
この扁桃体が障害されると、性行動が制御できず性欲亢進が見られたり、恐怖反応が欠落して温和化したり、飲食行動の制御が効かずなんでも口に入れるようになったりするなどの症状が見られます。
嗅覚
いわゆる「五感」の中で嗅覚以外は全て新皮質のところで説明しましたが、嗅覚だけは他にない特殊性を持っています。

まずは、嗅覚の伝導路について説明します。嗅覚は嗅上皮の嗅細胞が持つ化学受容器に匂い分子が結合することによって知覚されます。
嗅細胞は篩骨篩板(篩骨にたくさんの小さい穴が空いたもの)を貫く形で軸索を伸ばしており、嗅球内に存在する糸球体に到達します。
嗅細胞は受容する匂い分子によらず嗅上皮上にランダムに存在していますが、1種類の匂い分子に対する受容体を持っている嗅細胞は全て同一の糸球体に軸索を伸ばすというルールがあります。
糸球体ではシナプスが形成されており、ここでニューロンを乗り換えて嗅覚情報はさらに脳の中枢へ伝えられていきます。
これらの軸索は扁桃体とも繋がっており、これは嗅覚が上述の記憶や情動の回路と接点を持つことを意味しています。
最後に嗅覚の特殊性、他の五感とは異なる点を挙げます。
・一次受容器(視細胞など感覚を直接受容する細胞)である嗅細胞の軸索が嗅球という脳の中枢まで直接入り込んでいるという点
・他の感覚は感覚伝導の途中で視床を通るのに対し、嗅覚は通らないという点
・明確な一次感覚野が無い点。一次視覚野、一次体性感覚野などは明確な領域が決まっていますが、「一次嗅覚野」と呼ばれる明確な領域は存在しません。
これらの特徴は嗅覚が他の五感と比べて進化的に古い感覚であることに由来するとされています。
まとめ
この記事では大脳皮質の機能について網羅的にまとめました。
運動野、感覚野などは直感的に理解がしやすいですが、連合野の高次脳機能や大脳辺縁系の機能などは概念的にも複雑でありなかなか理解が難しい部分であると思います。
実際これらの分野は脳科学的に未解明な点も多い領域であり、無理に完全な理解を追い求める必要はないかもしれません。特に関わりの深い脳部位(記憶であれば海馬など)、および障害された時に起こる特徴的なエピソード(半側空間無視など)をそれぞれの機能と結び付けて覚えておくのがおすすめです。
✖️