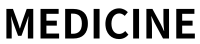医学部のCBT不合格から再試験合格を目指す方法を解説| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日:2025年11月15日
医学部4年次に全員が受験することになるCBT試験は、その後始まる病院実習に医学生が参加するのに十分な知識を有するか判断するのに使われる試験です。
まずは10月ごろに行われる本試験での合格を目指すことになりますが、万が一不合格になってしまった場合には再試験を受験することになります。
再試験でも不合格になってしまった場合、病院実習に進むことができず自動的に留年となってしまうため、絶対に落とせない非常に重要な試験です。
この記事ではその再試験に焦点を当て、合格を目指す指針を解説していきます。

監修
医師国家試験予備校MEDICINE 塾長 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
CBTで不合格になる原因3つ

まずは、筆者の経験をもとに CBTの本試験で不合格になってしまう医学生の典型的なパターンを3つ紹介します。
既に本試験で不合格になってしまった医学生は自分がどのパターンだったのかしっかり振り返ってください。
本試験をこれから控えている医学生は、このような状態にならないよう注意して試験対策に臨みましょう。
①演習量が不足している
不合格になるパターンの一つ目は「演習量が不足している」です。筆者の経験上はこのパターンで不合格になる医学生が最多です。
多くの人がCBTの対策としてクエスチョンバンク(QB)形式の対策問題集、特にMedic Media社のQBなどを利用していると思います。
QBには4000問近い問題が収載されています。CBTの膨大な出題範囲をカバーできるだけの知識をしっかりと定着させるためには、最低でもこの4000問の問題を2周以上解いて理解する必要があります。時間を空けて複数回同じ問題を解くことによって新たな知識の定着が促されるだけでなく、分野横断的な理解を得ることで、異なる疾患同士の病態の共通点が見えてきたり、症例問題でより適当な鑑別疾患をあげられるようになるなどの効果があります。
しかし、この量の演習をこなすにはかなりの長期間(3ヶ月〜半年ほど)計画的に問題を解き進めなければなりません。
計画的な勉強ができていなかったが故に、QBを1周解いただけでCBTに望まなければいけなくなった、場合によっては1周も終わらないまま試験当日を迎えてしまった、となると試験であまり良い結果は望めません。
②漫然と問題を解いただけになっている
不合格になるパターンの二つ目は「漫然と問題を解いただけになっている」です。
上述の通り、CBT対策をするにあたって問題数をこなすことはとても重要です。
しかし、それはあくまでも必要条件であり、多選択肢式の問題をただ漫然と繰り返し解いているだけでは、そのうち正解の選択肢の文章を丸暗記してしまったり、場合によっては選択肢の記号を覚えてしまったりして、本番で出題される初見の問題への対応が困難になってしまうことがあります。
特に、3周目以降になってくると見覚えのある問題も多くなってきて、時間をかけて問題を解き進めるのが面倒になり、つい選択肢の記憶だけで問題数を消化することになってしまいがちです。
初見の問題への対応力を高め合格に近づくためには、正解の選択肢がなぜ正解なのかしっかり根拠を持って選ぶ、逆に誤答の選択肢はどこが誤っているのか説明できるようにする、出題されている疾患の病態、診断、治療を答えられるようにするなどのアウトプットを伴った勉強が大事です。
③直前でやる気を失ってしまった
不合格になるパターンの3つ目は「直前でやる気を失ってしまった」です。
このパターンはある程度の長期間継続的に勉強を進めてきていた人が、同じ勉強を繰り返すことに対する億劫感やそれまでの積み重ねに対する安心感から、試験直前になってやる気を失い勉強するのをやめてしまう、いわゆる「燃え尽き症候群」です。
どれだけコツコツ努力を続けてきた人であっても、試験直前期にそれまでやってきたことの総復習をかける「追い込み」的な勉強は、あやふやだった知識を最後に完璧に定着させることにつながるため学習効率が桁違いに高くなります。
逆にこの直前期に勉強をサボってしまうと、知識が定着しないどころか、それまで覚えていたことまで忘れてしまうという二重のデメリットを受けることになります。
燃え尽き症候群を防ぐためには、
1周目:まずは問題を解いた後しっかり解説を読んで疾患に関する理解を深める
2周目:間違えた問題および記憶が甘かった事柄を箇条書きで記録しておく
3周目:2周目の時に間違った問題ができるようになっているか確認しつつ、問われていない周辺知識も確認して追記する
のように毎回勉強法をアップデートしていくやり方をしたり、口頭で人に正解の根拠などを説明しながら問題を解いていくなどのやり方をするのも効果的です。
再試験での逆転合格を目指す心構え

ここからは本試験の不合格が判明してから、再試験に臨むまでどのような心構えで対策をしていけばいいのか解説していきます。
簡潔に結論から述べてしまうと、再試験合格に必要なのは「本試験合格に必要な勉強を一から短期間で仕上げる」ことです。
どのようにこれを達成すればいいのか解説します。
本試験で落ちた理由を考える
再試験対策の勉強を始める前に、まずはなぜ自分が本試験で不合格になってしまったのか振り返るところから始めなければなりません。
特に自分では十分な対策をしたつもりで合格するはずだったのに落ちてしまったという場合には、一から勉強をしなおそうとしたところで、本試験の時と同じ轍を踏むだけになってしまう可能性が高いです。自分の勉強法のよくなかったところをしっかり理解し、再試験対策に反映させることが必要です。
CBTの合否はIRTというスコアを用いて判定されますが、これは正答率のような絶対的な基準ではなく、全医学部生の中での相対的な位置を反映したものです。言い換えれば、「合格した人と同じような勉強をし、同程度の理解を得られていれば十分合格できる試験である」ということもできます。実際にCBTをクリアしている医学生の勉強法も参考にし、自身の勉強法を見直すことも必要でしょう。
勉強の質・量ともに大事にする
単純に対策を始めたのが遅く勉強量が圧倒的に不足していたという場合には言わずもがなですが、前述の通り自分ではそれなりに勉強をした自覚があったのに落ちてしまったという場合には、本試験対策でやってきた勉強にそれ相応の原因・欠陥があり、試験の問題を解くにあたって十分な知識の定着や理解を得られていなかったと考えられます。
そのため留年を絶対に回避するという意味でも、再試験の勉強はそれまで勉強してきたことは一旦リセットして全てを一から学び直す心構えで始める必要があります。
・4000問程度あるQBの問題を2周以上解く(演習量を確保する)
・一つ一つの問題で正答の根拠、誤答の誤っている点を説明できるようにする(演習の質の維持)
少なくともこの2点は再試験での合格に必須と言えるでしょう。
ただ、前提となる知識が極端に少ないと1周目から質を保って、一問一問丁寧に解き進めていくのは非常に時間がかかりますし、何より精神的に疲弊してしまうことも多いと思われます。
このような場合には一周目はひとまず教科書などを手元に置いて、問題を解きながら解説の内容を理解することに徹し(説明できるほど深い理解は後回しにする)ベースとなる知識を得た上で、2周目以降丁寧に進めていくというやり方も有効です。
勉強では質・量どちらもおろそかにしてはいけませんが、勉強量を確保しないことには質を高めることは叶わないということはしっかり理解しておきましょう。
余裕のある勉強計画をはじめに立てる
これは決して「1日にやる量があまり多くならないような計画」(余裕を持ってこなせる計画)を立てるという意味ではありません。
本試験に不合格になってしまった時点で、すでに崖っぷちに立たされている状況です。
「再試験当日よりも1週間以上前に合格ラインに達するような計画」を立てるようにしましょう。
再試験での合格を目指すには、あらかじめ本番までにやる量を決めておいて、日数で割った分だけの量を毎日こなす以外に道はありません。
1週間前には十分合格ラインに達していて、最後は自分が間違えた問題を総復習して追い込みをかけられるようにしましょう。
まとめ
CBT再試験合格の鍵は、「本試験での失敗原因を正確に分析し、勉強法を根本から見直すこと」と「質・量を両立させた徹底的な演習」にあります。
特にQB問題を2周以上解き、正答の根拠や誤答の理由を理解するアウトプット学習が不可欠です。
焦らず計画的に、再試験の1週間前には合格ラインに達するスケジュールを組み、最後は弱点の総復習に全力を注ぎましょう。
再試験は決して簡単な道ではありませんが、正しい努力と工夫次第で十分逆転合格は可能です。
✖️