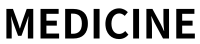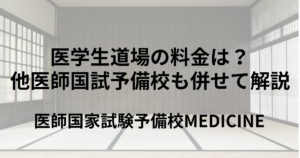医学部の共用試験CBT・OSCEとは?概要と対策について解説| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日:2025年11月15日
医学部在学中(多くは4年次)に受けることになる試験の一つにCBTと呼ばれる試験とOSCEと呼ばれる試験があります。
この二つの試験は、一般的に医学部の試験の中では医師国家試験の次に重く、対策が大変な試験とされていますが、特に1、2年生の方は名前は聞いたことがあっても実際にどんなことをやるのかは知らないという方も多くいらっしゃると思います。
実際、筆者も4年生になるまで「先輩たちがやたらに大変と言っている試験」程度の認識で中身についてもほとんど何も知りませんでした。
この記事ではCBT・OSCEについて、全く知らない方でもわかるよう試験の目的、概要から対策法までまとめて徹底解説していきます。

監修
医師国家試験予備校MEDICINE 塾長・医師 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。大手医師国家試験予備校で、在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。その後、医師国家試験予備校MEDICINEを設立し現在に至る。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
共用試験CBT・OSCEの目的

まずは、この二つの試験が日本全国全ての医学部で実施されている目的を解説します。
通常、医学部では4年生の前半まで座学で基礎医学、臨床医学を学び、4年生の後半から附属病院での病院実習を行うというカリキュラムが組まれています。この座学から病院実習に移行するタイミングで行われるのがCBT・OSCEです。
さて本題である試験の目的についての話に移ります。CBT・OSCEの目的は、「臨床実習において患者の診療に参加する学生の知識、態度及び技能が標準的な水準に到達していることを評価する」ことです。(厚生労働省「共用試験のホームページ」より引用)
もっと簡単に言えば、その医学生を病院実習に進めても問題がないかどうかを決める試験ということです。
そのため、CBT・OSCEのいずれか片方でも不合格になってしまうと「病院実習に進む資格がない」と判断されたことになり、自動的に留年となります。この意味でもCBT・OSCEは医学生にとって非常に重要な試験であると言えるでしょう。
公的な試験としてのCBT・OSCE

CBT・OSCEが医学部で行われる他の試験(定期試験など)と大きく異なる点は、「公的な試験である」という点です。
定期試験などは通常医学部の授業を担当した教員が問題作成、試験の実施、採点まで担いますが、CBT・OSCEの二つの試験は、そのすべてを公的な機関である「医療系大学間共用試験実施評価機構(CATO)」が行います。そのため、大学間で問題の難易度や採点基準に差が出ることなく、日本全国全ての医学生に対して同じ基準で「病院実習を行う資格があるか」が判定されます。
公的な試験ですので試験の実施方法や採点基準なども非常に厳格です。定期試験と違い、点数が一点でも足りなければ容赦無く不合格になりますし、追試験も1度しか実施されません。
ちなみに、CBT・OSCEの本試験、CBT追試験は通常自大学で実施されますが、OSCEの追試験は実施時期が近かった大学の本試験不合格者だけを一カ所の会場に集めて実施されるそうです。その会場は必ずしも大学の近くに設定されるとは限りません。筆者が受験した年は関西に設定されており、OSCE本試験に不合格だった場合、追試験受験料(数万円)に加えて交通費や宿泊費でかなり痛い出費になっていたそうです。
試験の概要CBT編

ここからは、CBT・OSCEの詳しい中身について、試験当日の流れ、出題される内容、採点・合否判定の基準の順に解説していきます。
試験について具体的なイメージを持っておくと、対策もしやすくなり、本番の緊張も和らげられるはずです。
試験の流れ
CBTの試験は所属する大学の中で丸一日かけて行われます。
基本的には朝早めの時間に集合時間が設定されており、大学に着いたら飲み物や昼食などを除く全ての荷物を用意された部屋に置いて、試験会場の教室に移動することになります。勉強道具などは試験終了まで一切見ることができませんので注意してください。
荷物を置いた後は、試験会場になっている教室と休憩場所として設定された教室のどちらかで過ごすことになります。
試験教室には1人1台試験を受けるためのPCが用意されています。開始時間になると自動的に問題がPCに表示され、全ての問題をそのPC上で回答します。
CBTの試験は6ブロック(+終了後アンケート)に分かれています。1ブロックの試験時間は1時間で間に10分間の休憩と昼食を取る時間が用意されています。時間は非常に厳格に管理されているので注意しましょう。ブロックの開始時間に1分でも遅れてしまうとそのブロックの試験は一切受けられなくなってしまいます。
夕方ごろに6ブロック目の試験が終了し、そのまま終了後アンケートに回答すると全ての項目が終了で帰宅することができます。
出題内容
出題されうる範囲は基本的に基礎医学から臨床まで、それまでに習った内容全てです。ただ、ブロックごとに出題形式が異なりますので解説します。
- ブロック1〜4
ブロック1〜4では5つある選択肢の中から正解を一つ選ぶ形式の問題が出題されます。基礎医学、臨床医学、公衆衛生など幅広い分野の知識を問う問題が出るほか、それらの知識を組み合わせて考察する問題も出題されます。
また、同ブロック内であれば、一度飛ばして後から解き直したり、見直して回答を変更することも可能です。
各ブロックの問題数は60問ずつです。
出題例
問:細胞内でRNAの情報を元にリボソームがアミノ酸を結合しポリペプチドを合成する過程をなんというか
①転写
②細胞分裂
③分化
④複製
⑤翻訳
- ブロック5
ブロック5では1〜4よりも選択肢の数が大幅に増えた(10コ程度)形式の問題が出題されます。ただ選択肢が増えただけで、問われる内容はブロック1〜4と同じです。基本的には正解はひとつで、「すべて選べ」のような問題は出題されません。しかし、選択肢の数が大幅に増えたことで勘で正解するのはかなり難しくなってしまいます。
とは言っても、しっかり理解していれば選択肢のほとんどは迷うことなく除外できるものばかりでそれほど恐れる必要はないでしょう。
このブロックでも1〜4と同様、戻って解き直すことが可能です。問題は40題出題されます。
- ブロック6
ブロック6では通称「4連問」と呼ばれる形式の問題が出題されます。4連問では、具体的な臨床のシナリオ(患者の情報、主訴など)が与えられており、そこから一続きになった4つの問題に回答します。問われ得る内容として多いのは、「他に患者に確認するべきこと」「行うべき検査」「診断」などです。
ここまでの5つのブロックと大きく異なるのは、戻って回答することができないという点です。これは、ある問題に対する答えが次の問題文に書いてあったりするためです。
問題数は全部で4×10の40問です。
出題例
76歳男性 食後に増悪する胃痛を主訴に来院
問1:患者に聞くべきことを選んだ時、最後に残るものはどれか
①症状はいつからですか?
②便の色に変化はありましたか?
③現在飲んでいる薬はありますか?
④ふらついたり、めまいを感じたりすることはありますか?
⑤ペットは飼っていますか?
問2:問診を行ったところ、症状は1ヶ月ほど前から持続しており、ここ1週間ほどは黒色便が出ていることがわかった。また、10年前に関節リウマチと診断されて以来継続してNSAIDsを服用していたこともわかった。血液検査を実施したところHb7.5g/dLであった。この患者で他に見られる可能性がある症状として不適切なものはどれか
①吐き気
②肩に放散する痛み
③吐血
④体重減少
⑤食欲不振
問3:次に行うべき検査として適当なものを選べ
①上部消化管内視鏡検査
②下部消化管内視鏡検査
③心エコー
④腹部エコー検査
⑤胸部X線検査
問4:上部消化管内視鏡検査を施行したところ、胃体部に多発する潰瘍を認めた。迅速ウレアーゼ試験は陰性であった。
この患者の病態に最も関わりが深いと考えられるものはどれか
①プロスタグランジン
②インスリン
③セロトニン
④ケラチン
⑤糖質コルチコイド
このように一連の流れの中で考察させる問題が出題されます。鑑別や病態をしっかり理解していないと正解するのが難しい問題が多く、CBTの6ブロックの中では最も難易度が高いと言えるかもしれません。
問3で②を選んだしまった場合のように、次の問題文を読んで1つ前の自分の回答が誤りだったことに気づくパターンもよくありますが、そこから先の問題が全て❌になったりはしません。落ちついて解き進め、取れる問題を確実に取れば大丈夫です。
採点方法・合否判定
CBTでは6ブロックで計320問が出題されますが、その中身は受験生によって異なります。数万問と言われる問題のストック(いわゆるプール問題)の中から、PCがランダムに問題を選び出題してくるためです。
これでは受験生によって当日解く問題の難易度の差が大きく異なってしまう可能性も考えられますが、それによって受験生間に不公平が生じないようIRT(項目反応理論)という仕組みが用意されています。これは、簡単に言えば難しい(受験生の正答率が低い)問題に正解すると多く加点され、簡単な問題に正解してもあまり大きくは加点されないシステムです。これによって、運に左右されず実力が点数に反映されやすくなります。
IRTのスコアは3桁の数字で出力されますが、一説によるとその数字は全医学部生の中での偏差値×10になっているそうです。(IRT500だったら、全医学部生の中での偏差値50ということ)合否判定もこのIRTスコアを用いて行われます。現在合格ラインは396(つまり偏差値39.6?)と定められており、これを1でも下回ってしまうと不合格です。
試験の概要OSCE編

CBTと同様にOSCEについても当日の流れ、出題内容、採点について解説していきます。
試験の流れ
OSCEはCBTより試験時間が短く通常半日で終了します。(筆者の大学の場合は学年が2グループに分けられ、午前試験の学生と午後試験の学生がいました)
会場到着後、全ての荷物を置いていき勉強道具の持ち運びが許されないのはCBTと同様です。
OSCEでは全部で8つの試験項目があり、項目ごとに用意された教室(以下ステーション)を5〜6人単位で回って試験を受けることになります。受験者間の情報伝達などを防ぐため、CATOの試験官による引率でステーション間を移動し、動線も厳密に管理されています。(移動の待機時間では他の受験者と目が合わないよう壁に向かって置かれた椅子に座ったりします。)
各ステーションごとに「救急」、「頭頸部診察」、「医療面接」のように大まかな項目は決められていますが、当日どんな問題が出題されるかは部屋に入ってみなければわかりません。部屋に入ると基本的に試験官数名と模擬患者(もしくはシミュレーターなど)が座った状態で待機しています。また、受験生がすべきことが「眼瞼結膜の視診」「アキレス腱反射の確認」のように指示された紙が置いてあります。
放送で試験開始の合図がなされ、制限時間内(だいたい5分)に指示された診察、手技を終わらせる必要があります。時間よりも早く終わった場合でも先に退出することはできず、終了の放送を待ってから退室します。
以上の流れを8ステーション分繰り返したら試験終了です。
出題内容
前述の通り、OSCEでは8つのステーションが用意されています。それぞれどのような課題が与えられるのか説明します。
- 身体診察
模擬患者に対して指示された診察を行う試験です。身体診察はさらに細かく「頭頸部」「胸部」「腹部」「神経診察」「全身状態とバイタルサイン」という5つのステーションに分かれています。視診、聴診、触診、打診などの基本的な診察の手技のほか、膝蓋腱反射などの神経所見の取り方、血圧の測り方など様々な手技を評価されます。
- 医療面接
こちらも模擬患者に対して医療面接を行う試験です。患者を診察室に呼び入れるところから始まり、主訴や現病歴、既往歴、生活歴といった情報を面接で収集し、最後に聞いた内容を要約するところまでが試験です。聞くべきポイントはあらかじめ決まっているのですが、どのような患者が来るかはわからないので練習で柔軟な対応をできるようになっておく必要があります。
- 基本的臨床手技
これは、採血もしくは心電図検査を行う試験で、いずれもシミュレーターを用いて行います。手技自体はそれほど複雑ではないですが、患者に危害が及ぶ恐れがある行為をしてしまうと大幅減点、場合によっては一発不合格となる可能性もあるので注意が必要です。
- 救急
医学生が臨床実習中に病院内で倒れているもしくは窒息している人を見つけたという設定で行われます。倒れた人という設定のシミュレーターのほかAEDや人工呼吸用マスクを持ってきてくれる通行人役が1人います。
①意識確認をしたところ応答がない(シミュレーターに大声で呼びかけると試験官が「反応がありません」と教えてくれます)
②助けを呼んでAEDとマスクを撮りに行ってもらっている間に自身は胸骨圧迫を行う
③AEDとマスクが到着したらそれらを用いて心肺蘇生を継続
④医師が到着し(程よいタイミングで試験官が「私は医師です。状況を説明してください」といってきます)状況を説明する
というのがオーソドックスな流れですが、倒れているのが子供だったり(胸骨圧迫と人工呼吸のやり方が大人と違う)、初めは意識があったのが途中で意識消失したりと色々なパターンがありかなり複雑です。フローチャート化してしっかり覚えておきましょう。
採点方法・合否判定
採点はCATOから派遣された試験官が行うようです。「患者への配慮」「身体診察」「医療面接」「基本的臨床手技」「救急」の5つの項目がありそれぞれにA ,B ,C ,Fのいずれかの評価がつきます。
評価がA ,B ,Cのいずれかであった項目は合格となります。逆に評価がFだった項目は不合格でその項目だけ追試験を受けることになります。
上述の通り、身体診察はさらに細かく5つのステーションに分かれており、それらの総合評価となります。そのため、どこか1箇所のステーションでミスをしたとしても、他でしっかり手技を行うことができれば、総合的には「身体診察」合格とみなされる可能性も十分にあります。
CBT・OSCEの対策方法

CBT・OSCEはとても出題される範囲が広く対策が大変な試験です。4年生の早いうち、場合によっては3年生のうちから計画的に対策を始めておくことで余裕を持って準備を終えることができます。ここでは、どんな対策や準備が有用なのかみていきましょう。
早めの時期から動画教材を活用
CBT・OSCEの対策はまず知識をインプットしてから、問題を解いたり手技を実際に行ったりするアウトプットを行うのが基本となります。
動画教材は特にCBTにおいてインプットに非常に役立ちます。大学の試験ではその授業を担当した教員の趣味が反映された問題が出題されたりするので、定期試験対策が必ずしもCBT対策になるとは限りません。その点、動画教材は基本的にCBT対策に特化して作られていますので無駄なく知識をインプットすることができます。
大学の定期試験に合わせて、動画教材を視聴し問題を解くというサイクル(「消化器内科」の試験があった週のうちに同範囲の教材を視聴しておくなど)
が確立できれば理想ですが、なかなかその通りにはいかないという人は少なくとも半年前には対策を始めるようにしましょう。
筆者の大学の場合、11月頭に行われるCBTに向けて、4月ごろから動画教材の視聴を始めていた人が多かったように感じます。
OSCEも同様に動画教材が用意されています。手技については文章で説明されたものを読むよりも、実際に手技を行っている様子を見て真似た方が確実に覚えやすいはずです。こちらもスケジュールは大学によって異なると思いますが、筆者の大学の場合、CBTの2週間後にOSCEが行われる予定となっており、ほとんど全員がCBT終了後にOSCEの対策を始めたような状態でした。その2週間は通常の授業がなく、すべての時間をOSCE対策に費やせる状態でしたので、それなりに余裕はあったように感じました。
アウトプットをしっかり行う
CBTもOSCEもインプットの後にアウトプットをしっかりと行うことがとても大切です。
動画教材はその特性上どうしても漫然と視聴するだけになってしまいがちです。そこで、例えばCBT対策であれば重要だと感じたポイントをまとめてみたり、視聴後すぐに問題を解いてみたり、OSCE対策であれば動画で行われた手技を実際に真似しながらやってみたりといったアウトプットを行いましょう。
前述の通りCBTでは320問が出題されますが、事前にどんなに多くの問題を解いて臨んだとしてもその中で「見たことがある」と言える問題は1〜2割程度のはずです。残りの8〜9割は持っている知識をもとに考えることになります。知識をベースにして臨床的な推論を行うのは慣れが必要です。同じ問題を繰り返し解くただの作業にならないよう、知識を頭に入れたら新しい問題にどんどん挑んでいきましょう。
OSCEの練習は友人同士で医師役と模擬患者兼評価者役に分かれてやるのがおすすめです。実際の人に対して行うことでより本番に近い形で練習できますし、評価者としての視点を持つことで自身の技術向上にもつながります。また、自分では気づかない癖や礼儀、アイコンタクトなどの部分について他の人の目で評価してもらうというのは意味があるでしょう。
最後に、CBT・OSCE共通して少しでも不安要素があると本番では緊張から大きなミスにつながりやすくなります。苦手意識があるところに気を取られすぎて、普段間違えたことのなかったところで手順を飛ばしてしまうというようなことがよく起こります。早めに対策を開始し、試験当日までにはすべての分野、項目で「完璧である」と言える状態にしておきましょう。
まとめ
ここまで共用試験CBT・OSCEについて試験の目的、概要、対策を見てきました。
CBT・OSCEで学んだことは当然その後の病院実習でも大いに役立ちます。CBTで学んだ知識を急に指導医から問われたり、担当患者にOSCEで学んだ診察をするよう指示されたりもします。
ぜひ小手先の丸暗記で試験を突破することだけでなく、病院実習を有意義なものにすることを目標にして自分のためになる勉強を心がけてください。
そうすれば合格は自ずと近づいてくるはずです。
✖️