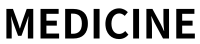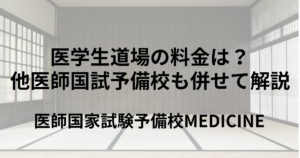脳神経12対の覚え方 語呂合わせも含めて解説| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日2025年11月15日
医学生は2年次または3年次に「解剖学」という分野を学びます。解剖学では大まかにいうと人体の構造について学習しますが、その中の重要な項目に「脳神経」というものがあります。この記事では12対ある「脳神経」について概説、覚え方を解説し、最後に1対ずつその特徴、役割などについて述べます。

監修
医師国家試験予備校MEDICINE 塾長・医師 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。大手医師国家試験予備校で、在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。その後、医師国家試験予備校MEDICINEを設立し現在に至る。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
脳神経とは

「脳神経」はヒトの体内に存在する末梢神経(対になる概念は「中枢神経」で脳と脊髄を指す)のうち、脳から直接出ているものを指します。脳神経に対して、脳から直接出ていない末梢神経は「脊髄神経」と呼ばれます。
脳神経は全部で左右12対存在し、脳から出る場所が前部のものから後部のものまで順番にⅠ〜Ⅻまで番号が振られています。(通常、脳神経の番号はローマ数字で表されますので慣れておきましょう。)
脳から直接出るという特性からも分かるとおり、多くの脳神経は眼や鼻、顔面といった頭部の器官に分布し支配しますが、中には僧帽筋のように首付近の筋肉を支配する脳神経もあります。
脳神経をすべて覚える理由

解剖学では、脳神経Ⅰ〜Ⅻ番までの名前だけでなく、その役割(支配する器官や交感神経・副交感神経支配など)、走行、分枝など多岐にわたる特徴を覚える必要があります。
複雑なうえに紛らわしいものもあり、量も多いですが、その分解剖学の試験やCBTの基礎医学範囲などで比較的出題されやすいです。確実にすべての項目を覚えておくのが大事です。
また、脳神経の障害は脳圧亢進や腫瘍、梗塞のような頭蓋内の病態を反映しており、眼球の運動障害や舌の運動障害、めまいといった特徴的な症状を呈することがあります。これらの症状は、OSCEにおける神経診察から5年生以降の病院実習、初期研修医として救急の初期対応を行うときまで、非常に重要になります。
これも、脳神経についてしっかり理解し覚えておくべき理由の一つと言えるでしょう。
脳神経12対の語呂合わせ

ここでは、まず導入として12対ある脳神経の名前をⅠ〜Ⅻまで順番に暗記する語呂合わせを紹介します。
名前から役割や分布などを関連づけて覚えられるものがほとんどなので、まずは12個すべて順番にそらで言えるようになりましょう。
以下に有名な語呂合わせと、神経の名前を列挙します。
- Ⅰ 嗅神経 嗅いで
- Ⅱ 視神経 視る
- Ⅲ 動眼神経 動く
- Ⅳ 滑車神経 車の
- Ⅴ 三叉神経 3つの
- Ⅵ 外転神経 外
- Ⅶ 顔面神経 顔
- Ⅷ 聴神経 聴く
- Ⅸ 舌咽神経 咽(ノド)の
- Ⅹ 迷走神経 迷う
- Ⅺ 副神経 副(副)
- Ⅻ 舌下神経 舌(ぜつ)
以上が12対の脳神経になります。
「嗅いで視る 動く車の 三つの外 顔聴く咽の 迷う副舌」という57577の語呂でまずは名前をしっかり覚えましょう。
脳神経12対を概説
ここでは、名前を覚えた12対の脳神経それぞれについて簡単に特徴や最低限覚えておくべきことを解説します。
それぞれの脳神経が頭蓋外に出る際に通る頭蓋底の穴(孔)についてもここで述べておきます。孔も非常によく問われるので合わせて確認しておきましょう。
まず初めに、各脳神経が脳から出る位置と、頭蓋外に出る孔の位置をそれぞれ以下に図で示しておきます。
適宜図で確認しながら読み進めてください。

上の図は脳神経が脳から出る位置を下から見上げる形で示しています。前の方から順番にⅠ〜Ⅻの番号が振られているのがわかると思います。

上の図は脳神経が頭蓋内から頭蓋外に出る時に通る孔の位置を頭蓋底を下から見上げる形で示しています。
各神経の説明にこの孔の名前を併記しますので確認してください。
Ⅰ 嗅神経
嗅神経は文字通り嗅覚を司る脳神経で「篩骨篩板」を通って頭蓋外に出たあと鼻の嗅上皮に分布しています。
嗅覚受容体がキャッチしたにおい分子の情報を脳に伝えるのが嗅神経の役割です。
嗅神経だけは例外的に孔ではなく「篩骨篩板」という骨にたくさんの細かい穴が空いた構造をとおて頭蓋外に出ます。
Ⅱ 視神経
視神経も文字通り視覚を司る神経で、「視神経管」を通って頭蓋外に出たあと網膜に分布します。
錐体細胞や桿体細胞のような視細胞がキャッチした光の情報を、脳の視覚野に伝える役割を担っています。
眼球を動かしたり、瞳孔の大きさを調節したりといった、視覚以外の機能は有していないので注意しましょう。
Ⅲ 動眼神経
動眼神経は眼球の運動を司る神経で、「上眼窩裂」という孔を通って頭蓋外に出て、動眼筋に分布します。(動眼筋とは眼球を動かす筋肉です。)
動眼筋には上斜筋、上直筋、外直筋、内直筋、下直筋、下斜筋の6つがありますが、このうち外直筋と上斜筋以外の4つを動眼神経が支配しています。
外直筋は外転神経支配、上斜筋は滑車神経支配です。紛らわしいですがしっかり覚えておきましょう。
動眼神経が障害されると片眼だけ動かせなくなり、ものが二重に見える(複視)などの症状が現れます。
また、瞳孔の大きさを緒節する役割を担っているというのも非常に重要です。
動眼神経が障害されると、対光反射(眼に明るい光を当てたとき瞳孔が小さくなる反射)に異常が生じたり、左右の眼で瞳孔の大きさが違う瞳孔不同が見られたりします。
動眼神経障害は脳ヘルニアなどの非常に重篤な命に関わる病態の予兆として知られており、救急医療の現場で動眼神経の所見は非常に重要になる場合があります。
Ⅳ 滑車神経
滑車神経も動眼神経同様眼球運動を司る神経です。「上眼窩裂」から頭蓋外に出るのも動眼神経と同様です。
滑車神経は上述の通り6つある動眼筋のうち、上斜筋を支配しています。
片側の滑車神経が障害されても複視が発生します。
Ⅴ 三叉神経
三叉神経は主に顔面の感覚と咀嚼筋の運動支配を行う神経で、名前の通り3つの大きな枝に分かれています。
三叉神経の3つの枝には上から順番に「眼神経」「上顎神経」「下顎神経」という名前がついています。それぞれの枝が脳神経Ⅴ番(三叉神経)の枝であることを強調してV1、V2、V3と呼ばれることもあります。
V1:眼神経はⅢ、Ⅳと同様で上眼窩裂を通って頭蓋外に出ます。主に額から鼻の上にかけての感覚を司っています。
V2:上顎神経は正円孔を通って頭蓋外に出ます。主に鼻から上顎(上唇)にかけての感覚を司っています。
V3:下顎神経は卵円孔を通って頭蓋外に出ていきます。V3だけは下顎の感覚のほか、咀嚼筋の支配も司っているので注意してください。
Ⅵ 外転神経
外転神経はⅢ・Ⅳと同様、眼球の運動を司る神経で、動眼筋のうち外直筋を支配しています。
上眼窩裂から頭蓋外に出るのもⅢ、Ⅳと同様です。
Ⅶ 顔面神経
顔面神経は表情筋および舌の前2/3の味覚、涙腺・唾液腺などを司る神経で、「内耳孔」を通って頭蓋外に出ます。
覚えておくべきこととしては、顔面の感覚は三叉神経、顔面の筋肉(表情筋)は顔面神経の支配であること、味覚は舌の前2/3だけを顔面神経が支配しているということです。
また、唾液腺には舌下腺、顎下腺、耳下腺の3つがありますが、顔面神経が支配しているのは舌下腺と顎下腺の2つです。
Ⅷ 聴神経
聴神経は聴覚と平衡感覚を司る神経で、顔面神経同様「内耳孔」を通って頭蓋外に出ます。別名「内耳神経」や「前庭蝸牛神経」とも呼ばれます。
聴神経は蝸牛に分布し聴覚を司る「蝸牛神経」と三半規管に分布し平衡感覚を司る「前庭神経」に分岐します。
蝸牛神経が障害されると聴覚障害が、前庭神経が障害されるとめまいや眼振が出現することがあります。
Ⅸ 舌咽神経
舌咽神経は、3つある唾液腺のうち耳下腺(残り二つは顔面神経支配)や、舌の後ろ1/3、咽頭や喉頭の一部の筋肉を支配する神経です。
「頸静脈孔」を通って頭蓋外に出ます。
顔面神経との支配領域の違いをしっかりと確認しておきましょう。
唾液腺については舌下腺、顎下腺が顔面神経、耳下腺が舌咽神経です。
味覚は舌の前2/3が顔面神経、後ろ1/3が舌咽神経です。
Ⅹ迷走神経
迷走神経は、一部の咽頭、喉頭の筋肉(特に発声に関わる筋肉)、胸腹部の内臓の感覚や平滑筋を支配する重要な神経です。
迷走神経も「頸静脈孔」を通って頭蓋外に出ます。
迷走神経が障害される、嚥下障害や嗄声、不整脈など多様な症状が出現します。
Ⅺ 副神経
副神経は胸鎖乳突筋と僧帽筋を支配する純粋な運動神経で「頸静脈孔」から頭蓋外に出ます。
支配する筋肉は上記の2つだけなので名前も覚えてしまいましょう。
Ⅻ 舌下神経
舌下神経も舌の運動を担う舌筋群のみを支配する純粋な運動神経です。「舌下神経管」と呼ばれる部分を通って頭蓋外に出ていきます。
まとめ
この記事では脳神経12対について語呂合わせを紹介し、12対それぞれについて概説しました。
脳神経は定期試験やCBTなど様々な試験でとても問われやすい分野です。また、臨床上重要な症状とも関連しています。
12対全てについて番号と走行、役割(運動、感覚、自律神経成分について)、障害されたときに見られる症状をしっかり押さえておきましょう。
✖️