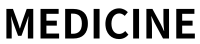医学生のマッチングとは?流れや仕組み、対策法を解説| 医師国家試験予備校MEDICINE
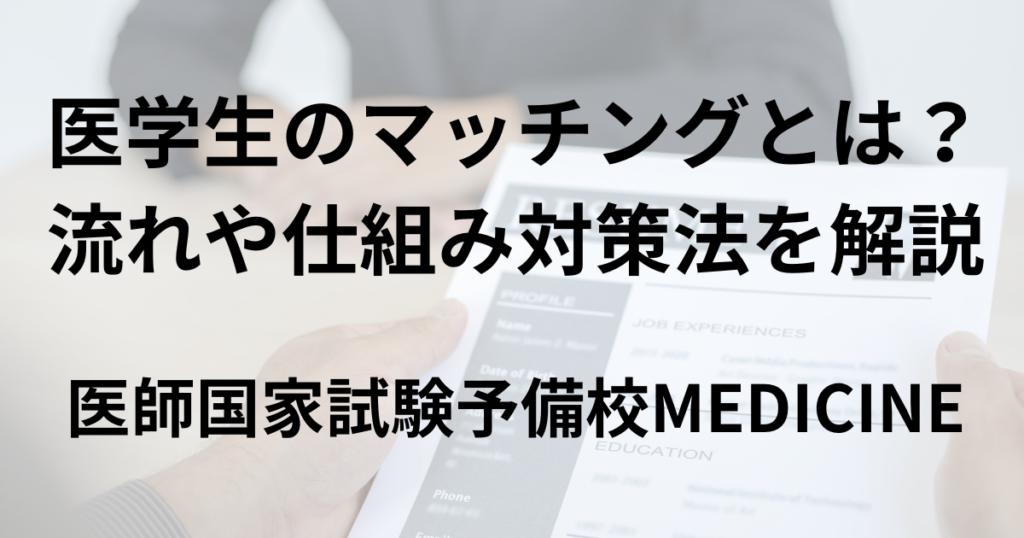
更新日:2025年11月15日
大学の医学部卒業後、医師として保険診療に携わるためには2年間の「初期研修」を必ず修了している必要があります。
この初期研修先の病院を決めるのがマッチングです。マッチングでは医学生側が研修を行いたい病院を、病院側が初期研修医として採用したい医学生を選び、双方の希望をマッチさせるという制度です。医学生から見れば、自分が研修を行いたい病院の採用試験を受ける就職活動のようなものになります。
全国の病院がさまざまな特色を持つ初期研修プログラムを展開しており、自分の描くキャリアを歩んでいくためにはその布石となる初期研修病院を選ぶことがとても大切です。
この記事では医学生のマッチングについて、「マッチングの流れ」と「マッチングの対策」について詳しく解説していきます。

監修
医師国家試験予備校MEDICINE 塾長・医師 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。大手医師国家試験予備校で、在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。その後、医師国家試験予備校MEDICINEを設立し現在に至る。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
マッチングの流れ

マッチングは医学生にとって歴とした就職活動であり、少なくとも医学部の5年生になった段階で計画的に準備・対策を進めていく必要があります。
ここでは、まずマッチングの全貌を把握していただくために、病院探しを始めるところから実際に採用が決定するところまで順を追って流れを説明していきます。
興味のある病院・プログラムを探す
マッチングの第一ステップとして、自分が将来の初期研修先として興味がある病院を探しましょう。
ひとくくりに「興味がある」と言いましたが、選び方の基準はさまざまあると思います。
例えば
- 大都市の病院 vs 地方の病院
あくまでも一般論ですが、大都市の病院の方が初期研修医を含めた医師の人数が多く、初期研修医に対する教育システムが整っていることが多いです。しかし、その分初期研修医はあくまでも「研修医」の立場であり、手術・手技を含めて実際の仕事を任される機会は少なくなりがちかもしれません。
一方、地方の病院では医師の数が不足がちであり、初期研修医も立派な「即戦力」として扱われ医師としての仕事を任される機会も多い傾向にあるようです。
また、地方と都会で初期研修医の給料にも大きな隔たりがあり、地方の病院の方が給料は高額である傾向にあります。
- ハイパー病院 vs ハイポ病院
いわゆる「ハイパー病院」というのは、救急患者数や手術件数などがとても多く「忙しい病院」ということになります。ハイパー病院では初期研修医の仕事量も膨大で(≠任される仕事の幅が広い)、当直の回数なども多くなる傾向にあります。
ハイポ病院というのはその逆で、そこまで忙しくはない病院ということになります。
忙しいからといって必ずしも初期研修医としてさまざまな経験が積めたり、良い教育を受けたりできるわけではありません。次の項目で説明する「病院見学」を通じて病院の雰囲気を掴みつつ、自分の体力とも相談して選ぶようにしましょう。
他にも病院選びの基準としては、「初期研修プログラム」で選んだり、自分の行きたい診療科が強い病院を選んだりといったものがあります。たとえば、将来外科医を志す学生であれば「外科プログラム」と呼ばれる外科の研修が充実しているプログラムに応募したり、外科の手術件数が豊富な病院を選んだりという具合です。
自分の希望に沿った初期研修ができる病院をまずは探してリストアップしましょう。
病院見学に行く
ある程度興味がある病院の整理ができたら、実際に病院見学に行きます。
多くの医学生は5年生の夏、遅くても6年生が始まる前の春休みには病院見学に行き始める人がほとんどです。
多くの病院はホームページに見学希望の医学生むけに情報を出しています。遅くとも見学を希望する日時の1ヶ月前には連絡を取るようにすると良いでしょう。
病院見学に行く大きな意義は、初期研修先として考えている病院に実際に足を運び、雰囲気を確かめられることです。その病院の初期研修医がどのような働き方をしているのか(定時で帰れるのか、当直やオンコールがどれくらいあるのか)、指導体制はどうなっているのか、どの程度の仕事を任されているのか見ておくと希望する内容の研修になりやすいでしょう。
また、研修そのものの中身以外についても実際に働く研修医に聞いてみるのが大切です。病院が持っている研修医療の綺麗さや病院周辺の環境(飲食店やコンビニ、アクセスなど)、研修医同士の仲の良さなども2年間を過ごすにあたって重要な要素と言えるでしょう。
マッチングの参加登録をする
マッチングの参加登録は例年6月ごろから始まります。この時点では、研修先として希望する病院を登録するのではなく、あくまでもエントリーするだけです。
大学からエントリー用のIDとパスワードが送られてくるのでそれをネット上で手続きして登録完了です。手続き自体は5分ほどで終わる非常に簡単なものですが、これを忘れてしまうと自動的にマッチングへの参加資格を失うことになります。忘れないうちに済ませておくようにしましょう。
病院の面接や筆記試験を受ける
マッチングの次のステップは病院ごとの採用試験です。
時期としては6年生の7〜8月ごろにまとめて試験を受けることになります。
まずは成績証明書や履歴書などの必要書類を病院に送るところから始まります。病院によっては書類選考である程度人数が絞られることもあります。
書類審査に通ると、どの病院でも必ず面接が行われます。面接では一般的な志望動機なども聞かれますが、コミュニケーション能力が十分あるか、その病院が求める人材であるかなどの観点から評価されることが多いようです。
また、人気が集中する大都市の病院では筆記試験が行われるところも多くあります。筆記試験は一般的に医師国家試験で問われる内容よりも高度な問題が出題されます。もしそのような病院を受けることを考えている場合には、5年生のうちから計画的に勉強を始めたり、病院見学で筆記試験の過去問をもらったりというような対策を初めておく必要があるでしょう。
希望順位を登録する
マッチングの最後に、希望する病院を希望順位とともにシステム上で登録します。
登録は6年生の9月ごろに行われます。
採用試験を受けた病院の中から選んで登録することができますが、その全ての病院を登録する必要はありません。逆に登録した病院とマッチした場合には、必ずその病院で研修をすることになります。断ることは基本的にできませんので、自分が研修をしてもいいと思う病院だけ登録するようにしましょう。
マッチングのシステム上では、病院側も採用試験を受けにきた学生に順位をつけて登録します。病院がつけた順位と学生の希望順位になるべく沿った形になるように選考が行われるようになっています。
しかしながら、医学生が第一希望として登録した病院とマッチする割合は、首都圏の病院の人気増大などを背景に年々減少傾向にあるようです。
もしマッチングに落ちてしまったら

システム上で登録したすべての病院に不合格になってしまうことを「アンマッチ」と言います。アンマッチになってしまった場合には基本的に「2次募集」に進むことになります。
1次募集で研修医の数が定員に達しなかった病院の一部は、マッチングの結果発表後に2次募集を開始します。2人募集は定員に達した時点で応募が締め切りとなり、人気な病院はすぐに空席が埋まってしまいます。アンマッチを確認したらすぐに2次募集を行なっている病院をなるべき早い段階で探し、自分からメールなどで連絡をとりに行くと希望する病院での研修に漕ぎ着けられる可能性が高まります。
病院側と連絡がついたら、その後は1次募集と同じように面接や採用試験を受けるという流れになります。
2次募集に回るのは基本的には1次募集でアンマッチとなってしまった学生ですが、中には国試浪人をしており勉強に集中するために労力のかかる1次募集をあえてスルーしているという特殊な例もあります。
マッチングの対策

マッチングは医学生にとって、その後の医師としてのキャリアに大きく関わる重要なイベントです。自分が希望する病院に就職できるように適切な対策を早い段階から始めておくことが大切です。
ここでは、マッチングの対策として重要と思われることをいくつか紹介します。
大学の試験、CBTの勉強をしっかりやる
一見マッチングには直接関係なさそうに見えますが、特に人気な病院の場合には書類選考でCBTの成績や大学の定期試験の成績証明を求められることがあります。
成績の利用方法は病院によって異なりますが、CBTの点数を書類選考の足切りとして用いたり、採用試験の点数に直接影響したりとさまざまです。
少なくとも、大学での成績が良い医学生の方が採用担当者にとっては好印象でしょう。
さらに、上述の通り筆記試験を課す病院では国家試験よりもレベルの高い問題が出題されることが多いです。直前で筆記試験の対策に追われないよう、CBTの段階からコツコツと勉強する癖をつけておいて、医師国家試験の対策にも5年生から入れれば理想的です。
筆記試験、面接の対策をする
求められる提出書類や採用試験の内容は病院によって大きく異なり、個々の病院に合わせた対策をするのは意外と労力がかかります。特に、書類提出の締め切りがある6〜7月ごろは毎日各病院の書類作成に追われてしまい、それ以外に割く時間がほとんど取れないということも十分考えられます。
一つ上の項目で述べた通り、直前には勉強時間があまり取れないことを見越して早めに対策を始めておく、または書類作成を早い段階から計画的にやっておくことが大切です。面接では、病院ごとに力を入れている点や理念に沿った受け答えができるとベストでしょう。必ず一度は受験する病院の基本理念などに目を通し、それを踏まえた志望理由、将来目指す医師像を答えられるようにしておきましょう。
次の項目で詳しく述べますが、病院見学の時に研修医の先生などから試験・面接対策について情報を得ておくのも大切です。
興味がある病院には複数回見学に行く
興味がある病院に見学に行き、指導体制や雰囲気が自分にっているのかを確かめるのは当然大切ですが、病院見学にはもう一つ重要な意義があります。
それは、複数回見学に行くことによって、自分の熱意をアピールできることです。特に初期研修先として強く希望する病院には2日×2回以上見学に行っておくのがおすすめです。多くの病院が集まる合同説明会に参加して直接話を聞いたり、複数回見学に行ったりして病院担当者に顔と名前を覚えてもらって不利になることはないでしょう。
また、見学を通じてその病院で働く研修医の先生と仲良くなれば採用試験(筆記試験)の情報を得たり、場合によっては過去問をもらったりすることもできます。実際にマッチングを通り抜けてきたばかりの研修医に対策のコツを聞く、他に受けた病院を聞いてみるなどすると自身のマッチングにとても役立つはずです。
まとめ
この記事では医学生のマッチングについてその流れと対策をまとめました。
マッチングは医学生にとって初期研修先を決める重要な就職活動です。5年生から計画的に病院見学を行い、雰囲気や指導体制を自分の目で確かめましょう。人
気病院では筆記試験や成績も重視されるため、CBTや大学試験の勉強を怠らず、早期から対策を始めることが大切です。面接では志望理由や将来像を明確に伝えられるように準備し、見学を重ねて熱意を伝えることで印象も良くなります。情報収集と早めの行動がマッチ成功の鍵です
✖️