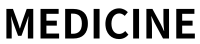問診のOPQRSTとは 覚え方と具体例を含めて解説| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日:2025年11月15日
医療の現場において、医療者が患者から情報を聴取するために行われるのが問診です。その際、最低限聴取すべき内容は決められています。特に、患者が訴える症状について聞くべき内容はそれらの頭文字をとって「OPQRST」と呼ばれています。
この記事では「OPQRST」の細かい中身と実際に問診を行う際のコミュニケーションの例を解説します。

医師国家試験予備校MEDICINE 塾長・医師 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。大手医師国家試験予備校で、在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。その後、医師国家試験予備校MEDICINEを設立し現在に至る。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
OSCE医療面接の問診

医学部4年次に行われるOSCEの試験項目の一つに「医療面接」があります。
これは、病院の初診外来において医師の診察前に医学生が医療面接(問診)を行うという設定で行われる試験です。
OSCEの医療面接以外の試験項目では「採血手技」「腹部の打診」「呼吸音の聴診」のように受験者(医学生)が行うべき医療行為が紙に列記された形で明示されています。事前にそれらを繰り返し練習してできるようになっておけば対応可能です。
それに対して医療面接では「模擬患者に対して問診を行う」という指示しか与えられていません。医療面接で聞くべき内容というのはある程度フォーマット化されているものの、それを試験中に確認することはできず、覚えておく必要があります。(参考記事)特に症状についてのOPQRSTでは、医学生が初対面の患者の主訴に応じて聞く内容を柔軟に変化させなければいけないというのも難しいところです。
医療面接で聞くべき内容に「家族歴」「服薬歴」などがありますが、これはすべての患者に対して「ご家族で大きな病気をされた方はいらっしゃいますか?」「何か薬は飲まれていますか?」のように同じ言い回しで対応可能です。一方、「OPQRST」については患者の主訴に応じて聞き方を変える必要があります。
次の「問診のOPQRSTとは」ではどんな主訴の患者にも対応できるよう詳しい中身を解説していきます。
問診のOPQRSTとは

問診のOPQRSTは症状について問診で聞くべき
・Onset
・Provocative/ Palliative factor
・Quality
・Region/ Related symptom
・Severity
・Time Course
の頭文字をとったものになります。
ここではそれぞれについて、具体的な内容と想定される回答などを詳しく解説していきます。
OSCEでは腹痛、胸痛など痛みが主訴であることが多いですが、発熱や全身倦怠感など他の主訴の場合にもこの問診法で対応可能です。
Onset 発症機転 いつからどのように始まったのか
症状の発症機転、いつからどのように(急に、徐々になど)始まったのかを確認します。
この質問は発症機序を推測するために重要であるほか、緊急性の判断にも有用です。
「1週間ほど前から軽い頭痛を自覚していたが、今日の明け方寝ている時に我慢できないほどの強い痛みを感じて目が覚めた」
「今朝起きた時体のだるさを感じ、体温を測ったら38.5℃の発熱があった」
など発症に至るまでの経過、発症した時の様子がストーリーとして理解できることが大切です。
Provocative/ Palliative factor 増悪/寛解因子 どんな時に良く/悪くなるのか
症状を悪化させたり、和らげたりする要因(行動)がないか確認します。
この質問は症状の原因となっている臓器の特定や、病態の推測に役立ちます。
例えば「食事をすると吐き気が悪化する」という訴えがあれば腹部の痛みを生じる疾患の中でも消化器系の疾患が強く疑われますし、
「体を動かすと痛みが悪化する」という訴えは筋骨格系の疾患を示唆します。
「症状が悪化したり、和らいだりするきっかけや状況はありますか?」のように質問すると伝わりやすいです。
Quality 質的内容 痛みの性質
症状、特に痛みの性質について質問します。
「どのような痛みですか?」と質問することで「ズキズキ痛む」「チクチクと刺すような痛み」「体中に響くような鈍い痛み」のように患者さん自身の言葉で痛みについて説明してもらいます。
特に「瞬間的に電気が走るような痛み」は神経系の異常を反映していたり、「周期的に強くなったり弱くなったりする痛み」は管腔臓器(消化管や子宮など)の平滑筋の収縮を反映していたりします。これも病気の原因を探る上で重要な質問です。
Region/ Related symptom 場所/随伴症状 症状の場所、他の症状
「症状の場所」については「どこが痛みますか?」のように質問して具体的に場所を示してもらいます。
「お腹」、「胸」などは範囲がかなり広いですので痛い場所を指でさし示してもらうのが良いでしょう。
「ピンポイントで痛い場所はわからないが、お腹全体がなんとなく痛む」というような情報も診断上非常に重要である場合もあります。
「随伴症状」では患者さんがはじめに訴えた症状(主訴)の他に症状がないか確認します。
病気を診断する上で重要な症状が、(複数ある中で)患者さんにとって最もつらい症状であるとは限りません。
「他に症状はありませんか?」のようにOpen questionの形式で質問してもいいですが、特定の疾患を疑う場合にはその疾患で想定される症状がないか具体的に質問しても大丈夫です。
痛みが主訴の場合、他の部位に広がる痛み「放散痛」の有無は心筋梗塞など致死的な疾患を鑑別する上で特に重要です。必ず確認するようにしましょう。
Severity 症状の強さ
症状の強さを質問し、重症度を確認します。
痛みの場合には「今まで感じたことがある最悪の痛みを10点とすると今の痛みは何点くらいですか?」のように質問し、点数化してもらう手法が多く使われます。
痛み以外の場合にも、「倦怠感が強く、水を飲みにベッドから起き上がるのもつらいほど」「吐き気はあるが、食欲があまりわかない程度で仕事には普通に行っている」のように日常生活にどの程度支障が出ているのかを確認することで重症度を測ることが可能です。
Time Course 発症後の経過
症状が出てから病院に来るまでの間にどのような経過を辿り、現在どのような状態なのか確認します。
単純に症状が良くなった/悪くなっただけでなく、どれくらいのスパン(時間単位、日単位、月単位)で変化があったのか確認することが病態や緊急性の把握に役立ちます。
問診におけるOPQRSTのコミュニケーション例

ここまででOPQRSTの細かい内容を確認してきました。
最後に医療面接を想定した具体的なコミュニケーションの例を示します。
OPQRSTは必ずしもこの順番で質問する必要はありません。
はじめに「今日はどうされましたか?」「そのことについて詳しく教えていただけますか?」というOpen Questionからはじめ、その後足りない情報をOPQRSTに沿って、会話として自然な流れ・順番で聞いていくことを心がけましょう。
コミュニケーション例
はじめに自己紹介、患者の本人確認を行い、医療面接を行うことの了承を得る。
(Open question)
医師「本日はどうされましたか?」
患者「お腹が痛くて診てもらうと思ってきました。」
医師「お腹が痛いのですね。痛みについて詳しく教えていただけますか?」
患者「はい。3週間前くらいからお腹の痛みが続いていて良くならないので、何か重い病気ではないか心配になって診てもらおうと思ってきました。」
(Onsetの確認)
医師「心配になっていらしたのですね。わかりました。それでは症状についていくつか質問させてください。3週間前から痛むとおっしゃっていましたが、痛みはどのように始まりましたか?」
患者「3種間前くらいの朝起きた時に、前の日まではなかったお腹の痛みを感じました。」
医師「3週間ほど前、朝起きた時に前日までなかった痛みを自覚したということですね。」
(Regionの確認)
医師「どのあたりが痛むか手で示していただいてもいいですか?」
患者(手で指し示しながら)「みぞおちのあたりが痛みます。」
医師「みぞおちのあたりですね。」
(Severityの確認)
医師「痛みの程度をお聞きしたいのですが、今まで感じたことがある最大の痛みを10点とすると今はどれくらいですか?」
患者「6〜7点くらいだと思います。」
医師「それはお辛いですね。日常生活に何か差し障りはありますか?」
患者「痛みで仕事に集中できず、影響が出ています。」
医師「仕事に影響が出るほどの痛みということですね。」
(Qualityの確認)
医師「痛みはどのような痛みですか?」
患者「鈍いような、胸が焼けるような痛みです」
医師「鈍くて胸が焼けるような痛みですね」
(Provocative/Palliative Factorの確認)
医師「痛みについてもう少し詳しくお伺いさせてください。痛みが強くなる時はありますか?」
患者「お腹が空くと痛みが強くなることが多い気がします。あとは、コーヒーを飲んだ時も痛みが強くなります。」
医師「お腹が空いている時とコーヒーを飲んだ時に痛みが強くなるのですね。逆に痛みが和らぐ時はありますか?」
患者「ご飯を食べると痛みが少し和らぐ気がします。」
医師「食事を召し上がると痛みが和らぐのですね」
(Related symptomsの確認)
医師「お腹が痛む時に、他の場所に痛みが出たり、別の症状が起きたりすることはありますか?」
患者「少しムカムカするというか、吐き気を感じることがあります。」
医師「吐き気を感じるのですね」
(Time Course の確認)
医師「3週間前からの経過についてお聞きしたいのですが、症状が出てから病院に来られるまでの間に痛みの強さなど変化はありましたか?」
患者「急に大きく変わったことはないと思うのですが、だんだん悪くなってきている気がします。」
医師「だんだん悪くなっているのですね。」
以下、既往歴、家族歴、生活・社会歴などを聴取する
まとめ
この記事では医療面接の中でもOPQRSTについて焦点を当てて解説してきました。
同じOPQRSTについても主訴の内容によって細かい言い回しは変える必要がありますし、患者の話す内容によっても順番を変える必要があります。
本番は時間がない上に緊張して焦りやすくなります。事前にさまざまな主訴に応じて対応できるように言い回しを含めて考えておき、ロールプレイなどの練習を通じてしっかりアウトプットも行いましょう。
✖️