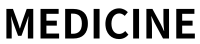OSCEに落ちる人の特徴は? 合格に近づく対策法も解説| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日2025年11月15日
医学部4年次、それまでの座学中心の勉強から病院実習へ進むにあたり全医学部生が受験することになるのがOSCE、CBTという二つの大きな試験です。
特にOSCEは臨床的な手技、医療面接の技能などを図る実技形式の試験であり、筆記試験とは少し異なる対策が必要になります。
この記事ではそのOSCE試験で不合格になりやすい人の特徴や、不合格にならないための対策法について解説していきます。

医師国家試験予備校MEDICINE 塾長・医師 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。大手医師国家試験予備校で、在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。その後、医師国家試験予備校MEDICINEを設立し現在に至る。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
OSCEの目的と出題内容

試験を実施しているCATO(医療系大学間共用試験実施評価機構)によると、OSCEの目的は
「臨床実習開始前の医学生が臨床実習で医行為を許容できる能力を有することを社会的に保障する」こと
です。
簡単に言えば、医学生が病院実習に進んでも問題ないかを大学間で統一された基準で評価するための試験であり、
・臨床技能
・医療者としてのコミュニケーション能力
が評価されます。
試験は、与えられた課題を受験生が試験官の前で模擬患者に対して実演し、それを評価される実技試験の形式です。
試験では以下のような課題が出題されます。
- 身体診察
身体診察の中にはさらに「全身状態の観察とバイタルサイン」「頭頸部」「胸部」「腹部」「神経」のような項目が設定されています。
体温や心拍数の測定といった簡単な診察から、呼吸音の聴診、腱反射の確認まで数多くの手技を覚える必要があります。
- 基本的臨床手技
採血、心電図測定、導尿(尿道カテーテル)からどれか一つが出題されます。どれも、衛生に気をつけ患者の安全に配慮した上でこなすことが求められます。一つ一つの手順が複雑ですので、繰り返し練習が必要になる試験項目です。
- 救急
病院実習中に人が倒れているのを発見したという設定の試験です。行う手技自体は、胸骨圧迫、人工呼吸、AEDの使用など複雑なものではないですが、条件分岐がかなり複雑です。
- 医療面接
初診外来で医師の診察前に医学生が問診を行うという設定の試験です。模擬患者に対して医療面接を行いますが、当然事前にどのような設定(主訴)の患者が来るかは分かりませんので、臨機応変に必要な情報を収集するコミュニケーションの能力が求められます。
OSCE合否判定基準

上記「身体診察」「基本的臨床手技」「救急」「医療面接」の4項目についてそれぞれ
・患者への配慮
・診察テクニック
という観点からA〜Fの6段階で評価されます。
患者への配慮、診察テクニックのどちらか片方でも「F」と判定された項目は不合格となります。
身体診察は頭頸部、腹部、胸部など複数の試験項目がありますが、それらの平均をとるような形で「身体診察」という一つの項目として評価されます。
詳しい説明は以下のページにありますので参考にしてください。
OSCEの本試験で不合格になった場合

OSCEの本試験で「不合格」と判定された試験項目については、その後1度だけ再試験を受験する権利が与えられます。
本試験で合格している領域については再試験を受験する必要はありません。
ただし、再試験で再び「不合格」と判定されてしまうと、その時点で病院実習に進めないことが確定し、自動的に留年となってしまいます。
また、再試験は受験料が数万円追加でかかる上、自身が所属する大学で受験できるとは限らず、かなり遠方まで受験しに行くことになる可能性があります。その点も十分注意しましょう。
OSCEで落ちるパターン

ここからは、筆者が実際にOSCEを受験した体験も元にOSCEで不合格になるのはどのようなパターンなのか解説していきます。
最後に不合格にならないための対策法も紹介しますので、ぜひご自身のOSCE対策に役立ててください。
禁忌を踏んでしまう
OSCEでは医師国家試験のように明確に禁忌が設定されているわけではありませんが、やってしまうと大幅減点となり不合格に限りなく近づく禁忌に近い行為は存在します。
実際の臨床の現場で行なってしまうと、患者さんに対して危害が及んだり、逆に医師自身の身が危険にさらされたりする可能性がある行為が禁忌に該当します。
具体的には
・アルコールでかぶれたことがある患者さんに対してアルコールで消毒をしてしまう
・採血で針を抜く前に駆血帯を外し忘れる。(駆血帯を巻いたまま針を抜くと傷口から血液が勢いよく噴き出す恐れがあります。)
・救急の人工呼吸を専用のマスクを用いず、口移しでやってしまう(倒れている人を発見した際、通行人役に「AEDを持ってきてください」とだけ頼んだ場合、本当にAEDだけが到着し人工呼吸のマスクは届かない)
・神経診察で爪楊枝を用いる際、尖っている方で患者さんに触れる
などの行為が該当すると考えられています。
不注意、もしくは単純な勉強不足からこれらの行為をやってしまい、不合格になるケースが一定数あります。
途中でミスをしてパニックになってしまう
実技試験で失敗したら留年がかかっているというOSCEの特性上試験本番はかなり緊張する人が多いと思います。
そんな中、試験の途中で自分がミスをしたことに気づいてパニックになってしまい、不合格になるというケースもかなり多いです。これは、特にしっかりと対策をして試験に臨んだ人こそ陥りやすいポイントであると言えるでしょう。
OSCEでは一つの試験項目で複数の課題、評価項目が設定されています。
例えば「神経診察」では眼球運動、顔面の感覚、徒手筋力テスト、腱反射のように複数の課題を与えられてそれらを順番にこなすことになります。また、採血のように単一手技の試験であっても、患者さんの本人確認を行うところから、採血が終わってゴミを分別して廃棄するところまで全てが評価対象になっています。
前述のような「禁忌」とされる行為を行なってさえいなければ、1つミスをしても他の手技を正確に行うことで十分合格点に達することができます。
しかし、試験の途中で自分のミスをしたことに気づいてパニックに陥り、そこから先の課題を正確に遂行できなかったり、またミスを帳消しにするため課題を全て最初からやり直して途中で禁忌を踏んでしまったりすれば不合格の可能性は一気に高まってしまいます。(例えば、採血で針を刺しても血が出なかったことに焦り、針を抜いて別の場所に刺し直したりしてしまうと、それは禁忌になります。)
時間が足りなくなる
OSCEでは医療面接が10分、その他の領域は5分という試験時間が設定されています。
これは決して十分な時間とはいえず、特に医療面接と身体診察の中の神経診察は時間が足りなくなる人が多いようです。
医療面接の場合には、その患者の診察をする上で重要と思われる質問を取捨選択して聞く、面接の最後に行う要約(総括)を残り時間に応じて手短に行うなどの能力が必要になります。
また、神経診察の場合には2、3回やって腱反射が出なかったら諦めて次に進むというような一種の割り切りも必要です。
とはいっても、時間が足りなくなるのは結局のところ練習不足に起因することが多そうです。本番を意識した練習で対策しましょう。
十分アウトプットの練習をしていない
教科書や動画教材などを用いて手順を暗記するだけで満足してしまい、十分なアウトプットの練習ができていないケースです。
自分では完璧に手順を覚えているつもりでも、いざやってみるとうろ覚えだったり、手技を間違えて覚えていたりということはよくあります。
医療面接については特にどんな出題があるのか事前には全くわからないので注意が必要です。
患者の主訴の内容、こちらの質問に対してどの程度まで回答してくれるのか、患者さんからどのような質問が来るのかによって対応の仕方を臨機応変に変える必要があります。
医療面接に限らず、普段からなるべく複数人と共同で、ミスをした場合を含めていろいろなケースを想定した練習をしておくのが大切です。
OSCEで不合格にならないための対策法3つ

ここからは、筆者が実際にOSCEを受験した体験をもとに、OSCEで不合格にならないために意識すべき点を3つ紹介します。
まずは大学の授業を大切にする
どの大学でもOSCE本番前に、試験で出題する実技について学ぶ授業があると思います。
この授業では、実際に現場で働く医師(通常は大学病院の先生だと思います)が授業に来て、手技を実演しながらやり方を教えてくれます。逆にこの授業はOSCE前に医師の先生から直接指導してもらうことができる唯一の機会です。授業の後は、教えてもらったことや教科書などを参考に学生同士で練習することがほとんどだと思いますので、手技のポイントや注意すべき点などを聞き逃すことがないよう集中して臨みましょう。
実技もただ単に動きを覚えるのではなく、「なぜそのようなやり方をするべきなのか」という視点を持つと理解が深まり忘れにくくなるはずです。授業を通じてしっかり理解しましょう。
授業で習ったことは、のちに演習するときのために教科書などに書き込んでおくのがおすすめです。
禁忌だけは必ず確認しておく
繰り返しになりますが、禁忌と言われている行為を行なってしまうと、大幅な減点を受けて限りなく不合格に近づくことになってしまいます。
また、禁忌は実際に病院実習で患者さんに対してやってしまうと直接重大な危害を加えたり、衛生の概念を無視していて(清潔なものを不潔に扱う行為)感染を引き起こしたりする可能性がある行為です。
責任を持って病院実習に臨むためにも、禁忌はぜひ事前に理由も含めて一度確認しておいてください。
また、禁忌とは少し異なりますが救急の試験では
・倒れた人を発見して意識がないことを確認した後すぐに助けを呼ばないと人が来ない(胸骨圧迫などを始めた後に助けを呼んでも人が来ないのでAEDが届かない)
・「AEDとバックバルブマスクを持ってきてください」or「救急カートを持ってきてください」と言わないと両方到着しない(「AEDを持ってきてください」だとAEDだけが持ってこられる)
というようなやってしまうとその先の評価項目に到達できなくなる可能性があるトラップも存在します。十分注意しましょう。
アウトプットとフィードバックを繰り返し行う
医療面接は臨機応変な対応が求められることからアウトプットの練習が重要であることは先に述べたとおりですが、その他の領域の対策でも単なる暗記にとどまらずアウトプットをすることは大切です。
OSCE本番は留年へのプレッシャーと、試験官に間近で見られているという構図からかなり緊張します。
そのような状況下では普段ならば絶対に起こさないミスも起こしやすくなります。
頭で次の手順を考えなくても、自然と手が動いてできる状態になるまで練習を積んで本番に臨むようにしましょう。
また、アウトプットの練習をする際は複数人で 受験生役と試験官役に分かれて行うようにしましょう。自身の勘違いのリスクなどを減らすことができるのはもちろんですが、細かい態度(髪を触る癖や貧乏ゆすり)、アイコンタクトなどは他人の目で評価してもらわないと気づくことができないものです。
また、自分が評価者の視点に立って細かいところまで批判的にみることで、自身の理解度を確認することもできます。特に採血などの手技で途中ミスをした場合の対処方法を話し合いながら練習しておくのも良い対策になります。
まとめ
この記事ではOSCEに落ちる人の特徴とそうならないための対策法について解説してきました。
OSCEは定期試験とは性質が異なる、臨床実習に進むための最低限の技能と態度を確認する大切な関門です。OSCE対策を通じて身につけた知識や手技、姿勢はその後の実習や医師としてのキャリアに直結する貴重な学びとなります。禁忌を避けるための基本知識の確認、限られた時間内で必要なことを遂行する練習、そしてアウトプットとフィードバックを繰り返すことが合格への鍵です。
本番では多少のミスがあっても冷静さを保ち、患者への配慮を忘れずに対応すれば十分合格できます。OSCEを単なる壁ではなく成長の機会と捉え、実習に自信を持って臨めるよう準備していきましょう。
✖️