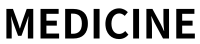呼吸の副雑音4つの覚え方について医師が解説| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日:2025年11月15日
CBTや医師国家試験では「呼吸の副雑音」についての知識が必要となる症例問題が出題されることがあります。
副雑音さえ理解していれば自ずと答えがわかるという問題も珍しくありません。
この記事では副雑音の中でも特に重要な「ラ音」と呼ばれる4つについて、音の特徴、発生機序、聞かれる病気について詳しく解説します。

監修
医師国家試験予備校MEDICINE 塾長 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
聴診で聞こえる音

胸部の聴診で聞くことができる呼吸に関連した音は、「呼吸音」と「副雑音」の二つに分類することができます。
呼吸音
呼吸音は、気道(気管〜肺胞)を通る空気が振動して聞こえる生理的な(聴取されることが正常である)音です。
呼吸音はさらに細かく以下の3つに分けられます。
・気管呼吸音
気管を空気が通り抜ける音で、頸部で聴取されます。
呼気時、吸気時の両方で聞こえる大きくて高い音です。
・肺胞呼吸音
肺の抹消付近で聴取されやすい呼吸音です。
吸気時のみ聴取できる小さい低い音です。
・気管支呼吸音
胸の中心部で聴取される、上二つの中間的な音です。
副雑音
生理的な音である呼吸音以外の異常な音を副雑音と呼びます。
副雑音もさらに「ラ音」と「胸膜摩擦音」に分けられます。
胸膜摩擦音は胸膜に炎症などがある際に、肺と擦れて聴取されるギュッギュという音です。
ラ音4つについては次のセクションで一つずつ細かく説明します。
副雑音4つの特徴、発生メカニズム

ここからは副雑音の中でもラ音と呼ばれる4つの音について解説していきます。
ラ音はさらに連続性ラ音と断続性ラ音に分かれます。
それぞれの分類の中にもさらに2つの音が含まれます。
このあたりは最後にまとめの図を作ったのでそちらを参考にしてください。
Rhonchi
連続性ラ音の一つで「ロンカイ」と読みます。
連続性ラ音は、狭窄して細くなった気道を空気が高速で通り抜ける際に発生する音です。
Rhonchiは気道の中でも特に太い中枢気管支の狭窄によって発生し、いびきのような低い音として聴取されます。
吸気時、呼気時の両方で聴取されるのも特徴です。COPDなどの病気で聞かれます。
Wheeze
Wheezeも連続性ラ音の一つで「ウィーズ」と呼びます。
起動の狭窄部を空気が通り抜ける音であるのは「Rhonchi」と同じですが、Wheezeの場合は狭窄部位が抹消気管支の場合に聴取されます。
中枢気管支よりもさらに細いところを通り抜けるので、Rhonchiよりも高い「ヒューヒュー」という笛のような音になります。
また、呼気時にのみ聴取されるという特徴もあります。気管支喘息で聞かれるというのも非常に重要です。
coarse crackles
ここからは断続性ラ音の話です。
Coarse cracklesは肺胞内に溜まった液体(主には痰)に空気がぶつかって聞こえる音です。
ストローを水に入れてゆっくり吹いた時のような「コポコポ」という音が断続的に聞こえます。
肺胞内に液体が貯留する疾患、肺炎、肺水腫などで聞かれる音です。
fine crackles
fine cracklesも断続性ラ音の一つです。
fine cracklesは肺胞の壁・間質が繊維化している(=硬くなっている)ときに聞かれる音です。
肺胞に空気が入る際に硬くなった壁が広がっていくことによって発生し、紙風船を膨らませた時のような「パチパチ」という音が断続的に聞こえます。
間質が繊維化する間質性肺炎で聴取されます。
呼吸音まとめ
以上が胸部の聴診で聴取される音になります。
最後にここまでで扱った音を一覧で図にまとめます。
用語の確認などに役立ててください。

✖️