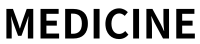post CC OSCEに落ちたらどうなる? 概要と対策方法について解説| 医師国家試験予備校MEDICINE

更新日2025年11月15日
医学部における医師国家試験前最後の関門として、6年次の夏頃にpost CC OSCEと呼ばれる大きな試験があります。この記事ではそのpost CC OSCEについて、不合格になるケースに焦点を当てて解説していきます。過去実際に不合格になった受験生のパターンも示し、最後に対策上重要なポイントについても解説します。
是非ご自身のpost CC OSCE受験に役立ててください!

医師国家試験予備校MEDICINE 塾長・医師 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。大手医師国家試験予備校で、在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。その後、医師国家試験予備校MEDICINEを設立し現在に至る。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
post CC OSCEとは

post CC OSCEとは医学部6年次の病院実習終了後に行われる実技試験で、国が定め全医学生が受験する公的な試験です。
post CC OSCEは実技試験であり、模擬患者に対する医療面接→診察→指導医(試験官)への症例プレゼンテーションという一連の流れをこなす課題や、採血、縫合などの手技を試験官の前で実演する課題などが出題されます。
4年次にも臨床実習前OSCE(以下OSCE)を全員受験しますが、その内容がさらに発展的になったものであると考えていただければ大丈夫です。
ここではOSCEとpost CC OSCEを比較しながらその特徴について解説していきます。
試験実施の目的
OSCE:病院での臨床実習に臨むにあたり、医学生が医療者として十分な技能、態度を修得しているか評価する試験、つまり医学生が病院実習を行っても良いか決める試験です。
post CC OSCE:病院での臨床実習を通じて、医学生が医学部卒業、初期研修開始に相応しい臨床能力を修得したか評価する試験、つまり医学生が卒業して初期研修をしてもいいか決める試験です。
OSCE、post CC OSCEともに大学間で採点基準などに不公平が生じず、全医学生を同じ基準で評価する目的で導入された試験です。
出題内容(臨床シナリオ)
OSCE:「口腔内の視診」、「腹部の触診」、「呼吸音の聴診」のようにやるべき内容が明示されており、それに従って診察を進めます。模擬患者は基本的に健康な人の設定です。(「医療面接」の課題は除く)
post CC OSCE:初対面の模擬患者に対して、医療面接を行い鑑別疾患(患者の訴えから想定されうる病気)を考えるところから始まり、必要な診察を自分で判断した上で、試験官に得られた情報、自分が考えた内容を整理してプレゼンします。
出題内容(手技)
OSCE:採血、心電図検査、などCATO(医療系大学間共用試験実施評価機構)が定めた手技の中から一つ出題されます。
post CC OSCE:各大学が独自に課題を出題します。筆者の大学の場合には採血などOSCEと同様の手技に加えて、縫合やカテーテル挿入、ガウンテクニックなどが出題されたことがあるようです。
以上OSCEとpost CC OSCEについて簡単に解説しましたが、より詳しい内容を知りたいという方は以下の記事も参考にしてみてください!
【医学部生向け】OSCE(オスキー)とは? 試験概要と対策について解説
post CC OSCEに落ちるとどうなる?

post CC OSCEは上述の通りかなり高度の臨床能力を要求される試験であり、不合格者も一定数発生します。
実際、筆者の大学ではpost CC OSCEの公的化(=採点、合否判定の厳密化)以降毎年20名前後が何らかの試験項目で本試験不合格になっているようです。post CC OSCEでは問題が全部で6問出題されますが、そのうちどれか一つでも不合格になってしまう人が毎年20名前後ということです。
万が一不合格になった場合でも1回は再試験の機会が用意されていることが多いようです。ただし、この再試験でも不合格になってしまうと卒業要件を満たせず、自動的に留年になってしまいます。
ただ、再試験に回ってしまうとその対策に時間を再び割かなければいけなくなってしまい、国家試験やマッチングの準備が疎かになってしまう可能性も考えられます。post CC OSCEで問われる内容は国家試験での出題と被る部分も多くありますので、早めから勉強を開始し、確実に本試験一発で合格するに越したことはないでしょう。
post CC OSCEで不合格になるパターン

post CC OSCEで不合格になるケースには一定のパターンが存在します。ここでは特に不合格になる人数が多いパターンを3つ紹介します。最後に、このパターンにハマらないための対策法も解説しますので、ぜひご自身の受験に役立ててください。
・疾患についての知識が十分でない
・時間配分をミスする
・手技で落とされる
疾患についての知識が十分でない
post CC OSCEの臨床シナリオに関する問題では
①模擬患者の主訴や病歴を医療面接で聞き取り鑑別疾患を考える
②鑑別疾患をもとに必要な診察を判断し正しい手順で実行する
③指導医(試験官)にプレゼンテーションする
という非常に高度な能力が求められます。この課題をこなすにあたっては当然出題されうる様々な疾患に関する知識を十分に持っている必要があります。
例えば患者が「胸痛」を主訴に来院したという設定の場合どのような疾患/病気が胸痛を起こしうるのか、胸痛を起こしうる病気をどのような手法(診察)で区別するのかといった知識を持っていないと、上記の①のステップをクリアできないことになってしまい、当然②、③でも良い結果は望めません。
十分な勉強をせず試験に臨んでしまった受験生が、このパターンで落ちる傾向にあると言えるでしょう。
時間配分をミスする
臨床シナリオの課題では上記の①医療面接と②身体診察を計12分以内に行い、③症例のプレゼンテーションを4分間で行うという時間制限が設けられています。与えられた12分をどのような配分で医療面接と身体診察に振り分けるかは受験生が自由に決めることができます。
出題されうる症候について十分勉強していった場合、「知識不足でどのような身体診察を行えば良いのかわからない、診察ができないのでプレゼンテーションも話すことがない」という事態は避けることができるでしょう。しかし、post CC OSCEに合格するためにはその知識を活かして「限られた時間の中で」、診察をおこない、自分の考えをプレゼンするという一歩先の能力が求められます。
過去実際に不合格になった事例でも、
「症候についてはしっかり勉強していったものの、重要度の低い(=診断につながるとは思えない)質問、身体診察を繰り返してしまい、診断につながる手がかりがほとんど得られなかった」
「勉強していったはずが、思い出すのに時間がかかってスムーズに進まず、やるべきことを時間内に終えられなかった」
「プレゼンテーションで重要なポイントを簡潔にまとめることができず、かなり初期の段階で試験時間終了となってしまった」
などのパターンが多くみられます。
また、各大学が独自に出題する臨床手技の試験でも
「手順自体はしっかり暗記していたものの、練習不足で何度も失敗してしまい結果時間切れ」
というケースも散見されるようです。
手技で落とされる
手技は大学によって出題される内容が異なる可能性がありますので、ここでは筆者の大学で過去実際に不合格となった事例について述べます。
まず、筆者の大学では臨床シナリオの課題と手技の課題とでは不合格者数に大きな隔たりがあり、2〜3倍程度も手技での不合格者数が多くなっています。
6年生の夏頃に実施されるのでマッチングの試験対策をしなければならないなどの事情もあり、座学ばかりに時間を割いてしまった結果、手技の演習が疎かになってしまうなどの理由が考えられます。当然、上述の通り時間制限で不合格になる受験生も一定数いますが、手順を動画などで確認するのみで手を動かす練習を怠ってしまい本番でミスをしてしまったというケースの方が多くみられます。
手技の試験では、成功失敗だけを評価されるわけではありません。例えば採血が出題された場合、「シミュレーターから血液を採取できれば合格」というわけでは決してありません。衛生操作(針の部分を不潔にしない)や患者への配慮(アルコールに被れるかどうかなど)、駆血帯の外し忘れ、廃棄物の処理(感染性廃棄物の概念)など採血を始める前から終了後の後処理まで全てが評価対象になります。
手技そのものをよく練習することも無論大切ですが、そのような細々した点の確認・勉強を怠った結果不合格になってしまったということがあります。
post CC OSCEで不合格にならないために

上の項目では筆者の経験に基づき、post CC OSCEで不合格になるパターンを紹介しましたが、ここではそうならないために重要な対策の考え方を解説します。
臨床シナリオの課題、手技の課題双方に言えることですが、まずは座学での勉強をしっかり行い十分な知識をつけましょう。
臨床シナリオの場合、出題される兆候はCATOの学修・評価項目(P86)で明示されています。まずはこれら37の症候について、考えられる疾患、それらを区別する身体診察の手法を全て覚えることが対策の第一歩です。数は非常に多いですが、単純に病気の羅列として覚えるのではなく、例えば「心不全では心臓の拍出能力が弱った結果、肺に血液が溜まってしまい、その血液から染み出した水分が痰となって咳が出る」というように病態の理解と合わせて覚えると覚えやすいだけでなく、マッチングや医師国家試験などその後の勉強にも非常に役に立ちます。
手技についても同様に、手技の開始から後始末まで「なぜその操作をその手順、その順番で行うのか」という理解と合わせて勉強することが第一歩です。
十分な知識を得たら実際の試験を意識した対策を行うことが重要です。知識を有していることと、それを限られた時間の中で適切にアウトプットできることはイコールではありません。
臨床シナリオであれば、友人と模擬患者役、試験官役、受験生の3人で実際の試験を再現して練習を行い、最後にお互いフィードバックをするという方法が有効です。そのような実践的な練習を行なっていく中で、「医療面接」「プレゼンテーション」については自分の中でフォーマットを確立できると理想的でしょう。
どれだけしっかり勉強をしていても、実践的な練習を積めておらずフォーマットが確立されていない状態やその場での思いつきで試験本番に臨むとどうしても焦りからミスを起こしたり制限時間を過ぎてしまったりするものです。練習でできなかったことが本番で突然できるようになることはないということを認識し、「本番では練習でやったことをそのままやるだけで大丈夫」という状態を作り上げましょう。
まとめ
post CC OSCEは、国家試験前最後の集大成とも言える重要な試験です。
大切なのは、知識と手技を「理解と実践」の両面から磨き上げ、限られた時間内で確実にアウトプットできる状態を作ることです。
post CC OSCEや医師国家試験自体はゴールではなく、その後の初期研修医として医師のキャリアをスタートさせるための通過点に過ぎません。初期研修を有意義なものにするためにも、post CC OSCE合格だけを目的とした一時的な勉強ではなく、その先の臨床や将来にしっかり活かせる学びを意識して取り組みましょう。
✖️