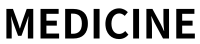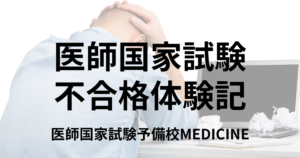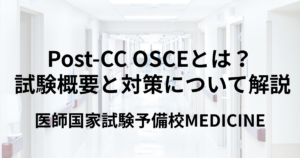禁忌肢とは?医師国家試験の過去問を例に解説 | 医師国家試験予備校MEDICINE
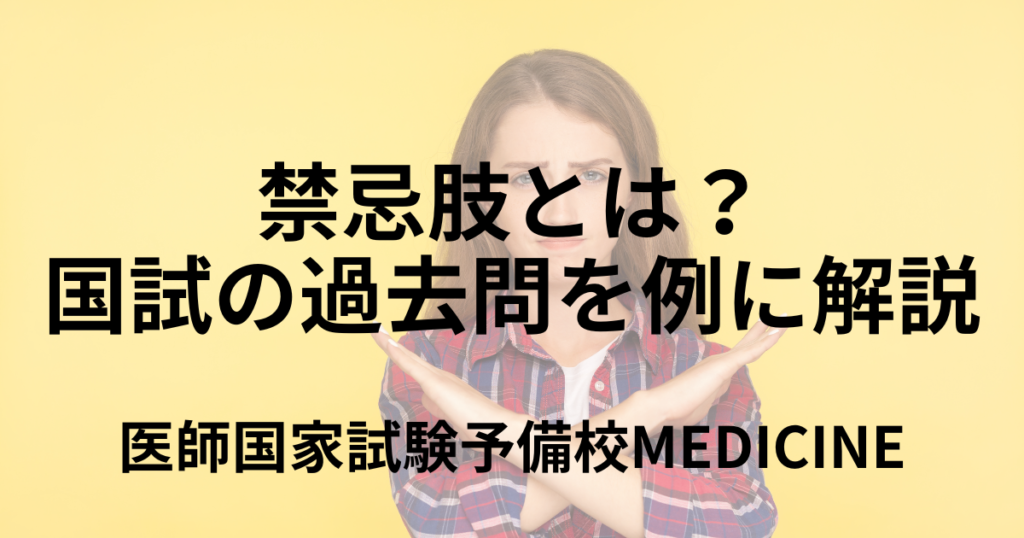
更新日:2025年11月15日
医師国家試験には、単なる知識だけでなく「臨床的な判断力」が問われる問題が数多く出題されます。中でも注意すべきなのが「禁忌肢」の存在です。誤って4つ(117回のみ3つ)以上選択すると一般臨床、必修の点数がどれだけ良くても問答無用で不合格となる選択肢のことを指します。
これらの選択肢は、いわば「絶対にしてはいけない医療行為」を意味しています。この記事では、禁忌肢の概要や出題例、対策法までを詳しく解説し、禁忌による失点を防ぐためのポイントをお伝えします。

医師国家試験予備校MEDICINE 塾長・医師 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。大手医師国家試験予備校で、在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。その後、医師国家試験予備校MEDICINEを設立し現在に至る。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
目次
禁忌肢とは?
「禁忌肢」とは、医師国家試験において選んではならない選択肢のことを指します。具体的には、患者に重大な害を及ぼす可能性のある誤った医療行為が記載された選択肢で、臨床現場では“絶対にしてはならない”行為を想定しています。
禁忌肢の歴史として、平成9年の第91回医師国家試験より導入されており、「患者の死亡や不可逆的な臓器の機能廃絶に直結する事項」が禁忌肢と定められています。 また、平成15年の医師国家試験改善検討委員会報告書において、 前述の内容に加え、「極めて非倫理的な事項」も明示的に加わり、禁忌肢として出題される可能性のある範囲が拡大して現在まで出題が継続されています。(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000693879.pdfより一部改変して引用)
このような肢を一定基準以上選ぶと、たとえ他の問題で高得点を取っていても、強制的に不合格となります。実際、「禁忌落ち」するケースは可能性としては低いですが0ではありません。国家試験を通して、正確かつ安全な医療を行える医師を育成するという目的のもと、こうした評価が導入されています。どの選択肢が禁忌肢となるかについては一切明かされておらず、基準も117回のように急に変わることがあります。そのため、禁忌肢である可能性が少しでもある場合は選ばないに越したことはありません。
なぜ禁忌肢が必要なのか

医師は人命を預かる責任ある職業です。国家試験での禁忌肢の設定は、単に知識量を問うだけでなく前述の通り「患者の死亡や不可逆的な臓器の機能廃絶に直結する判断ミスを避けられるか」を評価する意図があります。
患者を死亡させる/不可逆的な障害を残すなどの医療行為、または患者のプライバシーに配慮しない/研究不正を行うなどの非倫理的な行為を示唆する選択肢を選ばない能力は、現場での安全性確保/医師、医療への信頼の担保に直結します。
したがって、禁忌肢を選ばないことは「知っていること」ではなく、「臨床的、研究的に何をしてはいけないか」を判断する訓練の一環となっています。これは、現代医療/医学研究における“リスクマネジメント”の基本とも言える視点です。
医師国家試験に禁忌落ちする人はどれくらい?
実際に禁忌肢によって不合格になる「禁忌落ち」は、厚生労働省の公表する統計では明確には示されていません。また、最近は禁忌肢への研究が進んでおり、国試予備校の集計等でも禁忌落ちはほとんどいないのが現状であると思われます。
しかし、実際に禁忌落ちした方の成績表がネット上に存在する以上、禁忌肢が作用しているのも事実です。117回のように禁忌肢の選択問題数の基準が急に引き下げられることも十分考えられるため、実際に問題を解いているときに禁忌肢を選ばないようにするに越したことはありません。
医師国家試験で見られる禁忌肢の例
禁忌肢は必修問題・一般臨床問題問わず出題されます。以下に紹介するのは、過去の国家試験から実際に禁忌肢が設定されていたと考えられる問題です。設問の選択肢の中で、医学的に「やってはいけない」行為が含まれていた点に注目してください。
例1 119F62
甲状腺機能低下を呈している患者に対して、初療室での対応を聞かれている問題です。
76歳の男性.強いふらつきを主訴に救急車で搬入された.
現病歴:3ヵ月前から倦怠感やふらつきが目立ち,寒がるようになった.動作緩慢,便秘および経口摂取減少も出現したが加齢によるものと本人が思い様子をみていた.本日,倦怠感とふらつきが増強したため妻が救急車を要請した.
既往歴:1年4ヵ月前に中咽頭癌に対し化学放射線療法が施行され,6ヵ月ごとに定期通院中.
生活歴:70歳まで会社役員.妻と2人暮らし.喫煙歴はない.飲酒は日本酒1〜2合/日を40年間.
家族歴:弟が慢性肝炎.
現症:意識は清明.身長165cm,体重60kg.体温35.8℃.心拍数48/分,整.血圧98/68mmHg.呼吸数20/分.SpO2 97%(room air).皮膚は乾燥しているが,色素沈着は認めない.眼瞼結膜と眼球結膜とに異常を認めない.口腔内は乾燥しているが,咽頭発赤は認めない.頸静脈の怒張を認めない.甲状腺腫と頸部リンパ節とを触知しない.心音と呼吸音とに異常を認めない.腹部は平坦,軟で,肝・脾を触知しない.
検査所見:尿所見:蛋白(-),糖(-),ケトン体(-),潜血(-).血液所見:赤血球362万,Hb 11.7g/dL,Ht 35%,白血球4,100,血小板14万.血液生化学所見:総蛋白6.3g/dL,総ビリルビン0.5mg/dL,AST 34U/L,ALT 32U/L,LD 220U/L(基準124〜222),尿素窒素15mg/dL,クレアチニン1.1mg/dL,血糖92mg/dL,総コレステロール288mg/dL,Na 138mEq/L,K 2.8mEq/L,Cl 101mEq/L,TSH 98μU/mL(基準0.2〜4.0),FT3 1.8pg/mL(基準2.3〜4.3),FT4 0.1ng/dL(基準0.8〜2.2),コルチゾール12.4μg/dL(基準5.2〜12.6).CRP 0.1mg/dL.心電図は洞性徐脈でST-T変化を認めない.胸部X線写真で心胸郭比48%.
初療室で輸液を開始した.
次に行う対応で適切なのはどれか.
a 利尿薬静注
b ヨウ素含有食品摂取
c 甲状腺ホルモン薬内服
d 脂質異常症治療薬内服
e 塩化カリウム液急速静注
【禁忌肢】
「塩化カリウム急速静注」
【解説】
いかなる状況においても塩化カリウム静注は心停止を引き起こすため、絶対に行ってはならない医療行為となリます。このように、明らかに禁忌である選択肢も国試には登場しています。
例2 117D64
人工股関節術後に生じた股関節感染についての問題です
74歳の女性.右股関節痛を主訴に来院した.7年前に右変形性股関節症で右人工股関節置換術を受けた.その後,問題なく経過していたが,半年前から右股関節痛が出現し,徐々に痛みが増悪し歩行困難になったため受診した.意識は清明.身長156cm,体重46kg.体温37.2℃.脈拍84/分,整.血圧132/72mmHg.右股関節に腫脹と熱感を認め,発赤も伴っている.血液所見:赤血球370万,Hb 10.8g/dL,Ht 33%,白血球12,700,血小板30万.血液生化学所見:総蛋白7.4g/dL,アルブミン3.4g/dL,総ビリルビン0.6mg/dL,AST 17U/L,ALT 8U/L,LD 134U/L(基準120〜245),ALP 144U/L(基準38〜113),γ-GT 16U/L(基準8〜50),アミラーゼ70U/L(基準37〜160),尿素窒素12mg/dL,クレアチニン0.7mg/dL,血糖90mg/dL,Na 143mEq/L,K 4.0mEq/L,Cl 105mEq/L.CRP 6.2mg/dL.来院時の両側股関節X線写真で,右人工股関節にゆるみを認めた.
次に行うべきなのはどれか.
a 副腎皮質ステロイド関節内注入
b 下肢持続牽引
c 可動域訓練
d 関節液培養
e ギプス固定
【禁忌肢】
「副腎皮質ステロイド関節内注入」
【解説】
感染が考えられる場合、ステロイドの注入を行うとかえって感染が悪化し、最悪の場合股関節二不可逆な後遺症を残したり敗血症性ショックを誘発する危険性があります
例3 116B47
褐色細胞腫の降圧薬の選択についての問題です
次の文を読み,46,47の問いに答えよ.
20歳の男性.動悸と頭痛を主訴に来院した.
現病歴:17歳の時から時々動悸と頭痛を自覚していた.本日,知人の引っ越しを手伝うため家具を運ぼうとしたところ,動悸と激しい頭痛が生じ,内科を受診した.
既往歴:大学入学時の健康診断で血圧高値を指摘された.
生活歴:大学生.喫煙歴,飲酒歴はない.
家族歴:父が高血圧症で治療中.
現症:意識は清明.身長172cm,体重55kg.体温36.3℃.脈拍132/分,整.血圧192/110mmHg.呼吸数24/分.著明な発汗を認める.顔面は紅潮している.四肢に冷感を認める.胸腹部に異常を認めない.
検査所見:尿所見:蛋白(-),糖(-).血液所見:赤血球463万,Hb 13.2g/dL,Ht 40%,白血球5,800,血小板22万.血液生化学所見:総蛋白8.8g/dL,AST 24U/L,ALT 14U/L,LD 183U/L(基準120〜245),尿素窒素17mg/dL,クレアチニン0.8mg/dL,尿酸7.2mg/dL,血糖101mg/dL,Na 136mEq/L,K 4.2mEq/L,Cl 100mEq/L.CRP 1.2mg/dL.
入院後,以下の検査結果が得られた.
入院後検査所見:TSH 1.76μU/mL(基準0.2〜4.0),FT3 3.6pg/mL(基準2.3〜4.3),FT4 1.4ng/dL(基準0.8〜2.2),アルドステロン6ng/dL(基準5〜10),血漿レニン活性2.0ng/mL/時間(基準1.2〜2.5),アドレナリン120pg/mL(基準100以下),ノルアドレナリン1,200pg/mL(基準100〜450).尿中VMA 18mg/日(基準1.3〜5.1).腹部超音波検査で左側腹部に径2cmの腫瘤像を認める.
経静脈的降圧薬で降圧がみられたのち,最初に投与すべき経口降圧薬はどれか.
α遮断薬
b アンジオテンシン変換酵素〈ACE〉阻害薬
c カルシウム拮抗薬
d β遮断薬
e ループ利尿薬
【禁忌肢】
「β遮断薬」
【解説】
褐色細胞腫に対してβ遮断薬を単独投与すると血圧の急上昇を引き起こし、最悪の場合高血圧クリーゼを誘発する危険性があります。高血圧クリーゼも十分命を落としうる病態なので、禁忌肢となります
禁忌肢はいくつまで選べる?
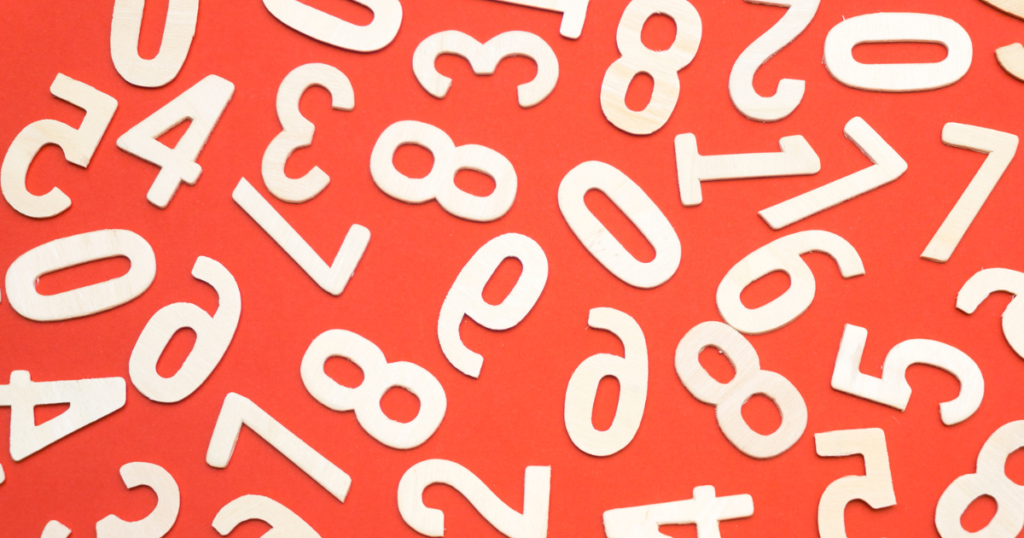
医師国家試験では、明確な基準点に加えて「禁忌肢」の累積数にも注目されます。一般的に、「禁忌肢を4つ以上選択した場合は不合格になる」とされており、これは全受験生にとって共通の評価基準です。
ただし、117回のように受験後に禁忌肢のボーダーラインが変わる可能性も十分ありえます。実際の国家試験受験時ではたとえ正解と思うような選択肢でも近畿市となる可能性が少しでもあるような選択肢は選ばないほうが賢明かと思います(少なくとも筆者はそうしていました)。
医師国家試験で禁忌落ちを避けるための対策

禁忌肢による失点は、事前の準備と意識づけによって十分に防ぐことが可能です。単に正解を選ぶ力ではなく、「絶対に選んではいけない肢を見抜く力」も日頃の演習で養う必要があります。以下に紹介する3つの具体策を日々の学習に組み込んでみてください。
普段の演習から禁忌肢を確認する癖をつける
禁忌肢を避けるための第一歩は、演習時に「どの肢が禁忌となりうるか?」という視点を常に持つことです。正答だけに注目するのではなく、誤答の中に潜む“危険な選択肢”を意識的にチェックすることが重要です。市販の問題集や過去問解説にも「禁忌肢」の注釈がついていることがあるため、それらを参考にするのも効果的です。
また、模試や演習の復習時に「禁忌マーク」を自分でつけておくと、再確認にも役立ちます。単なる知識問題ではないという意識をもって、危険な判断を排除する訓練を日常的に行いましょう。また、問題を解く際には本番の環境を想定することも大切です。禁忌肢は誤答選択肢とは違うマークで消去する癖をつけておくと本番の緊張した環境下ですぐに禁忌肢を判別することができるため効果的です。
医師国家試験のQBを使った勉強法についてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみると良いでしょう。
参考:医師国家試験のための勉強法|QBの使い方を東大卒講師が解説【2025年7月更新】
落ち着いて問題文を読む
禁忌肢にひっかかる原因の多くは、「焦って問題文を読み飛ばすこと」です。特に症例問題では、患者の全身状態やバイタルサイン、基礎疾患などが判断の前提になります。特に生化学データ、電解質には注意が必要です。薬剤に関しては投与経路別に病態の適応を考えることも大切です(アドレナリン筋注とアドレナリン静注の違いはなにか?など)
これらを丁寧に読み取らずに選択肢を選んでしまうと、適応外の医療行為を選んでしまい禁忌肢となることがしばしばあります。まずは冷静に状況を把握し、各選択肢の適否を文脈と照らして考える癖をつけましょう。時間に追われても、判断力を持って慎重に選ぶことが合格への近道です。
選択肢が正解か禁忌か迷ったら選ばない
選択肢に対して「正解かもしれないが、危険かもしれない」と感じたら、迷わず避けるのが鉄則です。禁忌肢は、その内容が患者に重大な害を及ぼす可能性があることがあるからです。実際に一般臨床は今までのボーダーを考えると300問中50〜60問は落としても合否に影響しません。必修に関しても2〜3個落としても合否には影響することは考えにくいです。一方で禁忌は4つ以上選んでしまうと無条件で不合格であることから「問題を間違えること」よりも「禁忌肢を選んでしまうこと」が遥かに大きいリスクとなります。
したがって、曖昧な知識で「たぶん大丈夫だろう」と選ぶのは非常に危険です。別の安全な選択肢があればそちらを優先し、確信の持てない選択肢は避ける判断力を持ちましょう。「危ない橋は渡らない」姿勢が、国家試験では非常に重要になります。
禁忌肢を選んでしまったらどうすればいい?

医師国家試験本番で禁忌肢を選んでしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。
もしも国家試験本番で禁忌肢らしき選択肢を選んでしまった場合、慌てるのではなく他の問題で確実に点を取る意識を持つことが大切です。1つの禁忌肢選択で即不合格となるわけではなく、他の得点状況や全体のパフォーマンスによって結果は左右されます。
また、「選んでしまったかも」と思っても自分の勘違いの可能性もあるため、過度に落ち込まず残りのブロックを確実に終わらせることに集中しましょう。また、1日目に禁忌肢である可能性が高い選択肢を選んでしまった場合には2日目はなおのこと注意して禁忌肢を選ばないようにすることが大切です。
試験後は自己採点を行いたい方は自己採点で結果を確認し、必要に応じて次回に向けた対策を立てましょう。自己採点を行わない場合は気持ちをリセットして2日目の受験を終わらせることが大切です。
まとめ
禁忌肢は、単なる誤答ではなく「命に関わるミス、または不可逆的な副作用をを防げるか」を問う重要な視点です。医師国家試験では知識だけでなく判断力が問われ、その象徴が禁忌肢の存在にあります。過去問や模試を通して禁忌肢に対する意識を高め、危険な選択肢を避ける習慣をつけておくことが、合格への近道です。「知っている」ことと「してはいけないことを避ける」ことは、試験対策の両輪です。自信と慎重さを持って、国家試験に臨みましょう。
✖️