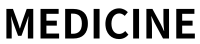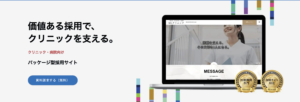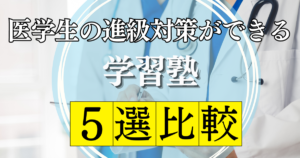医師国家試験のための勉強法|QBの使い方を東大卒講師が解説【2025年7月更新】
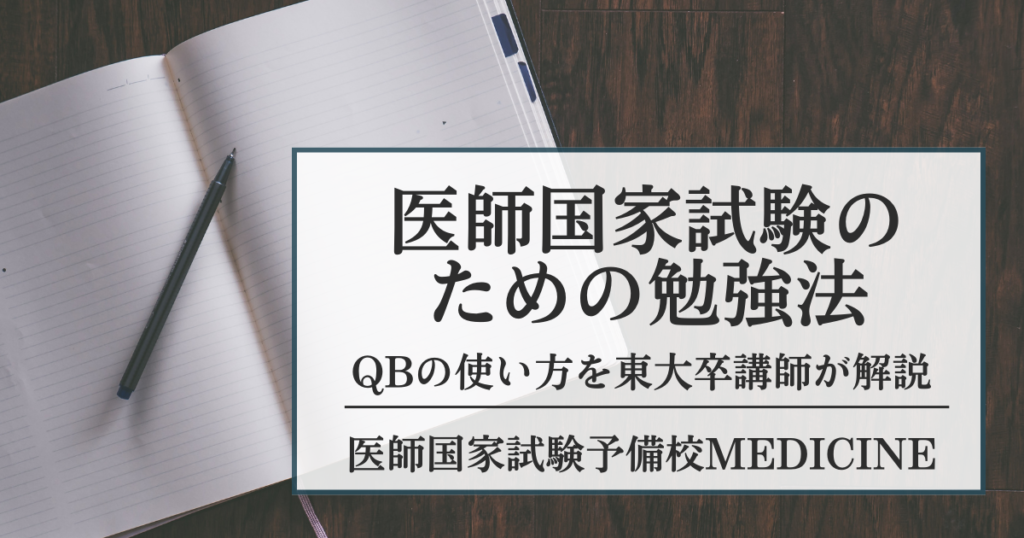
更新日: 2025年7月8日
医師国家試験は合格率が約90%と非常に高い試験であり、多くの受験生がQB(クエスチョンバンク)を利用して対策をしています。
しかし、QBを効率的に使った勉強法を本当に実践できている医学生は少ないのではないでしょうか。そこで本記事では、医師国家試験予備校での指導歴9年で、医学生の指導歴豊富な東大卒講師が、QBを最大限に活用した医師国家試験の勉強法について解説します。
ご紹介する勉強法は、医師国家試験対策で医師国家試験予備校MEDICINEを利用している受講生が実践している勉強法になります。
本記事の勉強法を活用することで、2024年2月に行われた第118回医師国家試験では全ての受講生が無事に医師国家試験に合格することができました。
また、これから医師国家試験対策を始める医学部5年生や4年生にも役立つ内容となっています。
- 医師国家試験まで残り数ヶ月しかないが、ここから効率良くQBを活用して、合格したい
- まだ5年生だが、医師国家試験に向けて早いうちからスタートを切って余裕を持って合格したい
このような医学生の悩みや疑問が全て解決される内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください!

監修
医師国家試験予備校MEDICINE 塾長 佐々木京聖
医師。東京大学医学部卒。医学生の個別指導歴9年。在学時より医学生の個別指導の経験を積む。基礎医学からCBT・国試対策まで幅広く手掛ける。
学生時代には、塾講師として延べ100人以上の大学受験生(主に医学部・東大志望者)も指導。東大理三をはじめ、医学部を中心に多数の合格実績。自身の勉強法をまとめた書籍に、学生時代の書籍『現役東大生が教える超コスパ勉強法』(彩図社)がある。
医師国家試験の勉強に不安はないですか?
医師国家試験予備校MEDICINEでは、指導実績豊富な東大卒医師による個別指導を受講することが可能です。
合格率も非常に高く、2024年の医師国家試験受験生、進級対策で利用されている受講生に関しては全員が医師国家試験に合格・あるいは進級試験・卒業試験に合格しています。
初回の無料面談では、指導実績・合格実績豊富な講師に30分間学習相談をしたり、アドバイスをもらうことができます。一人ひとりに合わせた学習戦略で、医師国家試験直前1ヶ月前からでも合格を目指すことが可能です!
- 1年に1回しかない国試で、本当に合格できるのか不安だ、なんとしても国試浪人だけは避けたい
- このままの勉強のやり方で大丈夫なのか、確認しておきたい
このような悩みや不安がある方は、ぜひ一度ぜひこちらからご相談ください!
目次
医師国家試験の全体像
まずはじめに、医師国家試験の概要について解説します。
試験の概要(科目、配点、難易度)
医師国家試験は毎年2月の上旬に行われ、2025年2/8(土)、2/9(日)に行われる試験は第119回の試験になります。
ご存知のように医師国家試験は必修問題と一般臨床問題の2つに分かれており、それぞれの問題数・配点・合格基準は以下のようになっています。
| 項目 | 必修問題 | 一般臨床問題 |
|---|---|---|
| 問題数 | 100問 | 300問 |
| 配点 | 200点 | 300点 |
| 問題の詳細 | 一般問題50問(各1点) 臨床問題50問(各3点) | 一般問題100問(各1点) 臨床問題200問(各1点) |
| 合格基準 | 絶対評価(8割=160点以上で合格) | 相対評価(一般には全受験生の上位9割に入る必要があると言われている。) |
二日間の試験スケジュール・時間割は以下のようになります。
1日目
- Aブロック・・・一般臨床問題75問(75点満点)
- Bブロック・・・必修問題50問(100点満点、一般問題25問、臨床問題25問)
- Cブロック・・・一般臨床問題75問(75点満点)
2日目
- Dブロック・・・一般臨床問題75問(75点満点)
- Eブロック・・・必修問題50問(100点満点、一般問題25問、臨床問題25問)
- Fブロック・・・一般臨床問題75問(75点満点)
医師国家試験の全体の合格率は例年90%を超えており、2024年2月に行われた第118回医師国家試験の合格率は92.4%でした。
合格率だけを聞くと非常に容易な試験に感じられるかもしれません。しかし、多くの受験生が1年前から入念に勉強を重ねて試験に臨んでいるため、計画的に勉強を重ねて対策しないと不合格になりかねない試験です。
また、第118回医師国家試験の合格率の内訳を見ると、新卒が95.4%、既卒生が58.9%となっています。国試浪人してしまうと合格するのがかなり難しくなるのがわかります。
国試浪人生の合格率が低い原因としては、病院実習などがないため現場感が薄れ、臨床問題に対応できなくなってしまうことや、約1年間という浪人期間、集中力を維持して勉強できないことなどが挙げられます。
最新の出題傾向について
医師国家試験の難易度は、ここ数年で大きな変化は見られていません。しかし、動画講座の普及に従う受験生のレベル向上により、一般臨床問題の合格点は年々上昇してきています。
直近の出題傾向では、単に知識を問う問題よりも、身体診察の方法など、より実臨床に近い問題が出題されるようになったことが挙げられます。
例えば、118B2では腹部骨盤部での触診法が問われました。さらに118B5では採血における具体的な手技が、118E12では腰椎穿刺による脳脊髄検査の手技が問われています。
このような手技は病院実習のローテーションで実践の中で覚えていくものなので、単に知識を丸暗記していく従来の勉強法では対応が難しくなってきています。
さらに近年ではAIの発展により単に鑑別診断をあげたり、治療法を提示するだけならAIの方が人間よりも優れた成績を残せることが各研究からもわかってきています。このような流れを受け、今後人間にしかできない身体診察を問う問題は増えていくと考えられます。
最新の出題傾向を把握するためにも、QBを活用して問題演習を行うことで、過去にどのような問題が出題されていたのかを理解していくことが非常に大切になります。
QBを活用した勉強法の具体例
医師国家試験の近年の傾向がわかったところで、QBを活用した具体的な勉強法についてレベル別に解説していきます。
医師国家試験本番までの残された時間や、現在の演習の進み具合によって行うべき対策方法は異なってくるので、ご自身の状況と照らし合わせながら自分にあった勉強法を選択するようにしましょう。
レベル別勉強法の大枠は以下の表のようになります。
| ステップ | 対象者 | 内容 | 目標 |
|---|---|---|---|
| 初学者 | 国試対策をこれから始める医学部4・5年生 国試対策を始めたばかりの医学部6年生 | メジャー科目・小児科・産婦人科から解き、解説を読む。 | 問題形式に慣れる。 勉強方法を確立する。 |
| 中級者 | メジャー科目のQBを一周終えた国試受験生 | 間違った問題、怪しい問題をまとめたノートを作る。 定期的な総復習を行う。 | ミスの傾向を分析する。 重点分野を強化する。 |
| 上級者 | 全範囲の問題演習を終えて、正答率が75%を超えている国試受験生 | マイナー科目や公衆衛生対策 本番さながらの問題演習 取るべき問題・捨てるべき問題を見極める。 | 合格点を取るための勉強 試験本番を意識した勉強環境の整備 |
初学者向け:メジャー科目から始めて勉強法を確立しよう
まずは、医師国家試験初学者の方向けの勉強法についてです。
ここでいう初学者とは、以下のような方のことを指しています。
- CBTが終わったばかりの医学部4年生
- 医学部5年生で、これから医師国家試験対策を始めようと考えている方
- 医学部6年生で、国試の勉強をまだ始めていない、あるいは始めたばかりの方
医師国家試験対策を始めたばかりの初学者の方が行うべきなのは、「基礎固め」と「勉強方法の確立」です。
医学部4年生・5年生の方は、こちらの記事でも「5年生からできる医師国家試験に向けた勉強法」を解説していますので、ぜひ参考にしてみてください!
はじめにメジャー科・小児科・産婦人科から解く
医師国家試験対策を始めたばかりの方でありがちなのは、、「QBを開いてもどこから始めればいいかわからず、時間ばかりが過ぎてしまった。」という失敗です。医師国家試験の試験範囲は膨大ですし、何から始めていけば良いのかわからないことも多いでしょう。
まずはQBのメジャー科目と小児科・産婦人科の問題から解いていきましょう。
具体的には、メジャー科目(内科、外科など)の問題を1日10問解き、解説を読み込むことから始めましょう。まだ医学部4年生・5年生の方はQBの1周目問題だけを解き進めるやり方もおすすめです。
メジャー科目・小児科・産婦人科から問題演習を始める理由は、これらの科目が医師国家試験の出題範囲の大部分を占めており、メジャー科目・小児科・産婦人科の科目の出来次第で医師国家試験の合否が決まると言っても過言ではないからです。
メジャー科目・小児科・産婦人科の基礎固めが早い段階でできていると、その後の公衆衛生、マイナー科目の勉強にスムーズに入ることができますし、必修科目の問題演習もやりやすくなります。
以下に、医師国家試験対策を5年生の11月から始めた場合の学習計画表の例を示します。
基本事項は動画講義で勉強し、毎週個別指導で定着度を確認しながら勉強をしていった場合のスケジュールです。
こちらのスケジュールのように、はじめはメジャー科目や小児科・産婦人科の勉強から始めていきましょう。
1問ごとに解説を読み込む
問題を解いたら、1問ごとに解説の確認を行なっていきます。
解説を確認するときに意識すべきことは、なぜ正解の選択肢が正解なのか、他の誤りの選択肢がなぜ誤りなのかを全て説明できるようにすることです。
解説に書いてあることを一言一句完璧に暗記する必要はありませんが、正解のポイント、誤りのポイントを要点を絞って説明できるようにしていきましょう。
はじめから高い正答率を出せる受験生はほとんどいません。はじめは正答率よりも勉強方法を確立する時間だと割り切って、演習を進めていくのが良いでしょう。

正答率は気にせず、はじめはメジャー科目・小児科・産婦人科の問題を一周することを目指しましょう。
これまでのMEDICINEの受講生を見ていると、6年生の前半までにメジャー科目・小児科・産婦人科の1周目演習を終えられた国試受験生は、はじめの演習の正答率に関わらず全受講生が国試に合格しています!
基礎を固めたら、次はミスを修正し、より得点力を高める中級者向けの勉強法に進んでいきます。ここでは、間違えた問題を分析し、効率的に復習する方法を解説します。
中級者向け:ミスの傾向を分析する
ここでいう中級者とは、メジャー科目・小児科・産婦人科の問題演習を一通り終えた国試受験生のことを指します。
正答率に関わらず、上記の主要科目の問題を一周すれば、医師国家試験のある程度の傾向が見えてくるのではないかと思います。
次のステップでやるべきは、自分のミスの傾向を分析することです。これまでの問題演習を通じて、QBで不正解になっている問題、あるいは正解したがもう一度やったら間違える問題(このような問題は△で印をつけておくと、後々復習しやすいです。)を中心に解き直していきます。
そして、怪しい部分、間違った部分を箇条書きで良いので、ノートに蓄積していきます。
ここで使用するノートは紙のノートでも、iPadなどの電子ノートでも、どちらでも構いません。
あとで復習しやすいように、情報を一箇所にまとめておくのがポイントです。
このように、間違った部分だけ、怪しい部分だけを一箇所にまとめていくと、自分のミスの傾向が見えてきます。
例えば以下のような具合です。
- 神経でも消化器でも、基本的な解剖の知識を問う問題の正答率が低い
- 癌の治療法の問題で、ステージ別の治療を問われたときに混乱してしまう
間違いの傾向がわかってきたら、その分野の教科書に戻って、復習を行なっていきます。
この勉強法により弱点が補強され、正答率が次第に向上していきます。
また、1週間に一回は、間違った問題、怪しい問題をまとめたノートを総復習する時間を作ると良いでしょう。繰り返し復習を重ねていくことで、はじめは覚えることができなかった知識も次第に暗記できるようになっていきます。
ここまでできたら、次は上級者向けの勉強に進んでいきます。
上級者向け:マイナー科目・公衆衛生の対策・模試の活用
上述した勉強を通じて、メジャー科目・小児科・産婦人科の正答率が上がってきたら、次は勉強範囲を医師国家試験全体に広げていきます。
マイナー科目・公衆衛生対策を行う
メジャー科目と同様の方法で、マイナー科目・公衆衛生の問題演習を行っていきます。
マイナー科目は科目ごとに出題される問題数はそれぞれ3~5問ほどなので、軽視して対策が最後まで遅れがちです。
しかし、マイナー科目自体の難易度はメジャー科目よりも高くないので、しっかり対策すれば確実に得点できる分野になります。
具体的な医師国家試験マイナー科目の勉強法に関しては、こちらの記事で詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてみてください!
また、公衆衛生は医師国家試験で出題割合が最も多い科目です。全問題における公衆衛生が占める割合は約17%と言われているので、勉強しないわけにはいかない分野です。
公衆衛生は他科目以上に、暗記することが多い分野です。ただ、試験範囲自体はそれほど広くなく、問題演習を積むことで頻出範囲はある程度見えてきます。具体的な勉強方法については、こちらの記事で詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてみてください!
試験本番を意識した問題演習を行う
問題演習で試験範囲全体を網羅できたら、模擬試験を活用していきましょう。
模擬試験は過去問にない問題が出題されるので、現在の自分の実力把握や、他受験生と比較した際の実力把握に役立てることができます。
模試を受ける際には、「解くべき問題」と「捨てるべき問題」を意識して臨みましょう。
「解くべき問題」というのは、多くの受験生(具体的には全受験生の80%以上)が正解できる問題のことを言います。
ご存知の通り、医師国家試験は合格率の非常に高い試験ですので、誰もが取れる問題を確実に得点していくことが合格への鍵になります。
一方、「捨てるべき問題」というのは、正答率でいうと50%以下の問題のことです。これらの問題は本番で不正解になったとしても合否に響くことはほとんどありません。
模擬試験で養うべきは、どの問題が取るべき問題で、捨てるべき問題なのかをしっかり見極める練習をすることです。
普段QBで問題演習を行っているだけではなかなか養えない能力ですので、模擬試験を活用して本番の感覚を掴んでいきましょう。
医師国家試験における問題演習の重要性
ここからは、すべての受験生に共通する事項として、問題演習の重要性や具体的な勉強法、直前期の過ごし方について解説していきます。
まず、医師国家試験の対策をする上で、なぜたくさんの問題演習をする必要があるのでしょうか。ここでははじめに、問題演習を行うメリットと、QBを利用するメリットに分けて解説していきます。
問題演習を行うメリット

問題演習を行うメリットとしては大きく分けて次の二つになります。
- 記憶の定着に有利である点
- 周辺知識が身につく
医師国家試験の試験範囲は膨大で、覚えなければならないこともたくさんあります。
必要事項を頭に叩き込むには、ただ参考書を読むのではなくアウトプットしたほうが記憶に残りやすいです。
さらに試験に出やすい情報の取捨選択は、問題演習(特に過去問)を通して初めてできるようになります。
ただ参考書を読んでいても、試験でどこが狙われるのか、どの部分が大切なのかを理解するのは難しいです。
例えば、医学部の進級試験で分厚い医学書を通読したけれど、どこが大切かわからなかった、と言う経験をしたことがある方は多いでしょう。参考書をただ頭から読むだけの勉強法は非常に効率が悪いので、国家試験の合格を目指すという意味ではやめた方が良いでしょう。
それよりも、数年分の過去問を解いて狙われ安い部分を理解し、その部分に絞って対策を行なっていくべきです。
また、QBの解説には各選択肢の解説だけでなく周辺知識も書かれています。
問題演習とともに周辺知識を身につけることは効率的な学習といえるでしょう。
正解の選択肢を覚えるだけではなく、なぜ他の選択肢が間違っているのかを、解説をじっくり読み込むことで理解することが大切です。これにより、新しい問題が本番で出てきた時にも、これまで問題演習で培った知識を使って、解答を導くことができるようになります。
QBを使用するメリット

QBは、今や医師国家試験受験生のほとんどが使用しています。
QBを利用することには、以下のようなメリットがあります。
- 各選択肢の正答率が信頼できる
- 自分の演習状況がグラフに表示され、学年内での自分の位置がわかる
- イヤーノートや病気が見えるなどの参考書と連携している
特に、現在の自分の演習状況がわかる(今まで解いた問題数と正答率を、他の受験生と比較できる)上に、前年度同時期のQB使用者(つまりちょうど1年前の1つ上の先輩)の演習状況と、最終的な国家試験での正答率がはっきりわかります。
前年度国試の成績が下位20%であった人と似た場所に自分がプロットされればさらなる演習が必要だとわかりますし、上位20%のプロットに重なっているなら順調に勉強できているだといえるでしょう。
他の受験生の進捗を知ることは、モチベーション管理に役立つだけでなく、復習のタイミングの指標にもなります。
これまでの数多くの医学生を指導してきて分かったことですが、国試で上位20%の人と下位20%の人の違いは、問題の数ではありません。
そうではなく、復習を含めた正答率なのです。(横軸が同じ3000問でも、縦軸の正答率75-80%あたりを境に、国試での成績が大きく異なってくると言う統計データがあります。)
つまり、どれだけ問題数をこなすかよりも、間違った問題をいかに復習するかが、合格への近道であるのです。
合格に向けた継続的な演習
QBは6000問近くあり、一朝一夕にこれをこなすできません。
したがって、継続的に問題演習を行う必要があります。
問題演習を継続的に行なっていく方法としておすすめなのが、以下のような方法です。
- 病院実習で学んでいる科の1周目問題を解いてみる
- マッチングで国試の過去問が出る病院を受け、その範囲に該当するQBを解く
これにより、短期的な解くべきQBの問題数がはっきりし、問題演習も継続しやすいです。
しかし、実際問題私が通っていた大学でも、病院実習に合わせて進められている人はごく少数でした。実習で回る科のローテーションは早いので、アルバイトや部活動などの予定なども踏まえると、計画通りに進めるのはかなり難しいようです。
QBを使った具体的な演習方法
では実際に、どのようにQBを使用していけば、医師国家試験の効率的な対策ができるのでしょうか。
ここでポイントになるのは、以下の3つになります。
- 1周目問題、メジャー科から解く
- 先を見据えて演習スケジュールを立てる
- 間違えた問題を徹底的に分析する
1周目問題、メジャー科から解く
国試までまだ時間がある5年生や6年生の前半では、科ごとに1周目問題をこなしてみましょう。
このとき正答率が半分を切るようであったり、継続が困難だったら、動画講義を見直すなどしてある程度知識がついた状態で進めるのも良いでしょう。
分野はメジャー分野から解くと、全体の概要をつかみやすくて良いでしょう。
もしマッチングの筆記試験などでメジャー分野などの特定の分野がよく出題されるなら、QBの「問題セット」を作るのが良いです。例えば、マッチング直前は過去5年のメジャー科の問題演習セットを作ります。全体の問題数でいうと1100問強になるので、このセットでひたすら問題演習をこなしていきます。
この際偶然正解した問題や、直前に講義を聞いていたために解けた問題などは、△をつけてあとから見直しやすくするとよいでしょう。
もし最新年の問題セットがマッチングなどで出題されないようでしたら、あえて解かずに残しておき、直前期に演習するのもおすすめです。
先を見据えて演習スケジュールを立てる

6年生の夏くらいまではマッチングや実習のスケジュールに合わせてQBを解いていきます。
6年後半になると1周目問題以外やマイナー科も十分に抑えておく必要があります。
しかし、医師国家試験の試験範囲は膨大であるため、6年前半までに行った演習内容をすべて覚えているとは限らないのが難しいところです。
過去に間違えた問題や△をつけた問題(+心配なら正解した問題も)と新しい問題を科ごとに進めていきます。
6年生の冬ごろまでにはすべての問題を解き終えておくと安心できます。
直前期の過ごし方としては、国家試験では5年分の過去問が非常に重要ですので、再度正解した問題も含め5年分復習しておくのが良いです。
5年分を年次で演習することで、2,3年前の問題が使い回されていることが実感できると思います。
医師国家試験の学習計画の立て方で悩んでいる方のために、学習計画表のテンプレートを添付しますので、ぜひ活用してみてください!
間違えた問題を徹底的に分析する
間違った問題をそのままにしては、成績は伸びていきません。次へ次へと新しい問題を解こうとするのではなく、一問一問を分析するのが大切です。
間違えた問題を分析する上で参考にすると良いのが、他受験生の正答率です。
正答率95%以上の問題は、常識的な問題か、過去数年にほぼ同じ問題が出た可能性が高いです。
前者の問題を落としていた場合は、その単元の勉強が足りておらず、弱点である可能性が高いです。
一方、後者の問題を落としていた場合に関しては、必要以上に焦る必要はありません。数年前にその問題が出たかどうかは、QBの「受験生の声」というコラムの部分を参考にするとわかります。
実際の国試で捨て問の場合も、QBの解説にそう書かれていることが多いです。一方、教育的な問題で正答率が90%前後やそれ以下の場合は、翌年度以降に繰り返し出題される可能性があるため、理解して解けるようにするのが良いでしょう。
また、間違えた問題や自信のない問題は、付随するQBのリンクからイヤーノートも見ておくと理解が深まります。
QBを解き始めた段階ではわからない問題も多いと思いますが、2周目、3周目で同じ間違いをするなどした場合は別にノートにまとめたりしてもよいでしょう。
医師国家試験予備校MEDICINEでは、指導実績豊富な東大卒医師による個別指導を受講することが可能です。
初回面談では、指導実績な豊富な東大卒医師に無料で30分間学習相談をしたり、アドバイスをもらうことができます。
- 1年に1回しかない国試で、本当に合格できるのか不安だ、なんとしても国試浪人だけは避けたい
- このままの勉強のやり方で大丈夫なのか、確認しておきたい
このような悩みや不安がある方は、ぜひ一度ぜひこちらからご相談ください!
QBを使用した演習上の工夫と注意点
ここまで、QBを使った基本的な勉強方法について解説してきました。しかし、他受験生と同じことをやっていても、差をつけることはできません。
そこでここでは、他受験生よりも一歩抜きん出るための勉強方法について解説します。
ポイントは、以下の3つになります。
- Medlinkアプリの効果的に活用する
- 最終目標を設定する
- まとめノート、暗記カードを作成する
Medlinkアプリの効果的に活用する

先程も述べた通り、QBの問題集にはイヤーノートや病気が見えるのページ数およびリンクが記載されています。
これを利用すれば学習効率は上がりますが、その他にもMedlinkアプリには有効な機能があります。
まずは検索ボタンです。すでに多くの方が使われているかもしれませんが、アプリの検索窓から好きな用語で検索するとメディックメディアの書籍(電子版を購入したもの)の、その用語に該当するページを見ることができます。
QBの解説では理解しきれなかったり、さらに周辺知識を知りたい場合は是非使ってみてください。
また、最近の受験生にはQuick Checkも好評のようです。
Quick Checkは国試の過去問数年分からエッセンスのみを抽出して一問一答の○×クイズとして解くもので、自分の正答率が低かったQBの問題を中心に出題してくれるので直前期に重宝します。

最終目標を設定する
試験本番で取りたい、合格点を必修・一般臨床ごとにあらかじめ立てておきましょう。
最終目標は国試に合格することですが、その中でも必修80%、一般臨床65-70%, 禁忌肢3問以下(一般臨床は年によって変動、禁忌肢は年によって2問以下)が必要です。
一昔前は一般臨床のボーダーは軽視されがちでしたが、ここ数年はそのボーダーが上がってきているため、どのセクションも気が抜けません。
前述の、正答率が高い問題は絶対に落とさないという意識で演習に取り組むのが良いでしょう。
医師国家試験予備校MEDICINEでは、本番での目標点数を必修90%、一般臨床80%に設定するように指導しています。
指導歴9年の東大卒医師の指導により、試験1ヶ月前からでも合格を十分目指せますので、一度相談してみたいと言う方は、こちらからご連絡ください!
まとめノート、暗記カードを作成する

まとめノート、暗記カードの作成を試験範囲全体に対して行うのは、6年生後半以降で良いかと思います。
ある程度演習を積んできて出やすいポイントがつかめてきたら、自分に足りない知識を暗記カードに落とし込んだり、まとめノートを作成するのが良いでしょう。
QBを解いていて正解以外の選択肢の解説などで新しい知識があれば、Ankiというスマホアプリを使って、Ankiデッキに含めるようにしましょう。
また、試験直前期に頻出ではないものの不安であった知識(小児の発達のニッチな部分や皮膚科など)はまとめノート(iphoneのメモ程度ですが)にまとめましょう。
医師国家試験の直前期にやるべきこと
医師国家試験は毎年2月の上旬にあります。
試験直前の12月から1月での期間は何をするべきなのでしょうか。自身の経験、そしてこれまでの受講生を見ていて絶対にやっておくべきなのは以下の3つになります。
- 過去問5年分をやり直す
- まとめノートを復習する
- 模試を解いて実力を確認をする
過去問5年分をやり直す

直前期はとにかく過去問5年分を完璧にする意識で過ごしましょう。
本番でも過去問5年からそのまま出る出題される可能性すらあります。
余裕がある方は、必修はもう少し昔の問題を遡ったり、公衆衛生のややこしい部分をまとめたり、今までの暗記カードなどを復習するなどして過ごしましょう。
直前期から新しいことに手を出す必要はありません。
これまで使用してきた教材を復習したり、今まで解いてきた問題集を解き直すのがおすすめです。
生活リズムを整えることも重要で、特に試験本番1ヶ月前からは、に実際の試験と同じ起床時間で外出し、勉強するという対策もすると良いでしょう。
まとめノートを復習する
勉強しているとどうしても、何回やっても覚えにくい部分は出てきます。
それらの知識を、ノートにまとめておくなど、何らかの形で試験直前期に見直せるようにしておくと良いでしょう。
ですが、1からノート作る必要は必ずしもありません。
講師の私が受験生の頃は、公衆衛生と必修以外はiphoneのノートにまとめておき、公衆衛生はQassistで使った板書、必修がレビューブックをまとめノートとして用いました。
国家試験は6ブロックありますが、公衆衛生が出やすいブロックが(少なくとも私の代までは)あったので、その直前に公衆衛生のまとめノートを、必修ブロックの前に必修のレビューブックを見ていました。
必修と公衆衛生に苦手意識がある方は、以下の記事も参考にしてみると良いでしょう。
模試を解いて実力を確認をする
模試は自分の現状位置を把握するうえでも重要です。トリッキーな問題も中には含まれているので、完璧主義になりすぎないように復習しましょう。
個人的な印象としてはテコム(現M3)模試は難易度が高いが練られた問題が多く受験者も多いです。
メディックメディアは重箱の隅をつつく問題もかつては多かったですが、近年ではその割合も減ってきたという印象です。
QBと似た感覚でPCで解くことができ、便利ですし、映像授業で解説もついています。
映像授業の中で、重箱の隅をつついた問題は解説してくれるので復習のメリハリがつきやすいです。
メックも問題の質が高く受験者も多かったイメージです。
直前期の模試は、実際の試験のスケジュールに合わせて外で解くのも本番のシュミレーションになって良いでしょう。
試験当日の過ごし方
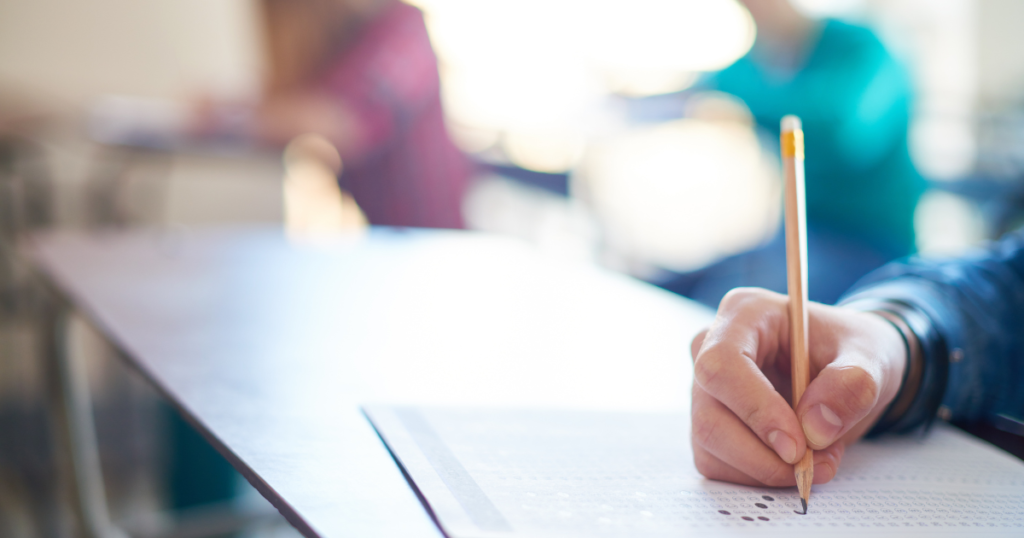
実力を出し切るためにも、当日気をつけることはチェックリストとしてリスト化しておくべきです。
医師国家試験予備校MEDICINEの受講生には、本番でチェックするべきことをノートやスマホに見える形でリスト化しておくようにお話ししています。
例えば、
- 選択肢を一つ選ぶ問題で二つ選びがち
- 問題文で読み間違えやすい部分をリスト化
- 1日目を終えたときにどのくらい1日目の復習をするのか(しないか)
- 何時までに寝るか
上記のように、自分なりに本番注意するべきことをリスト化しておくと良いでしょうk
試験中にやるべきことだけでなく、休憩時間、そして本番当日に家で帰った後にするべきことなどまでリスト化して、最善の体制を作るべきです。
ここまで準備をしたら、当日はいつも通り過ごしましょう。
試験会場は大学とは異なれど、周りには同じ大学の知り合いも多いので、リラックスして受けることはできる環境だと思います。
医師国家試験が終わったら、最後のお休みを楽しもう
自分なりに臨床に出た際知っておきたい知識があれば復習するのが良いですが、臨床現場に出たあとは2ヶ月の休みはなかなか取りづらいかと思います。
初期研修が始まるまで、長期の旅行にいくもよし、リラックスするもよし、新しいことを始めるもよし、休みを最大限使うのもこれから社会人として働くうえでの良いメリハリになると思います。
医師国家試験が終わったら、合格発表までは、思う存分最後の春休みを楽しみましょう!
医師国家試験予備校MEDICINEでは、指導実績豊富な東大卒医師による個別指導を受講することが可能です。
初回面談では、指導実績な豊富な東大卒医師に無料で30分間学習相談をしたり、アドバイスをもらうことができます。
・一年に一回しかない国試で、本当に合格できるのか不安だ
・このままの勉強のやり方で大丈夫なのか、確認しておきたい
このような悩みや不安がある方は、ぜひ一度ぜひこちらからご相談ください!
✖️